2011年09月10日
台風14号は熱帯低気圧へ、不安定な週末(9月10日)
(「紀伊半島の大雨の本当の理由!!」・・・興味がある方は6日の記事をどうぞ)
| 14時50分追記 気象庁は、明日正午までに台風15号が発生することを予想しているようです。 <11日12時の予報> 存在地域 日本の南 予報円の中心 北緯 20度40分(20.7度) 東経 137度20分(137.3度) 進行方向、速さ 西 20km/h(10kt) 中心気圧 1000hPa 中心付近の最大風速 18m/s(35kt) 最大瞬間風速 25m/s(50kt) 予報円の半径 220km(120NM) 今朝のGSMシミュレーションモデルでは、台湾方面へ進むことを予想されていますが、他国のシミュレーションの中にはやや北上を予想しているものもあります。 明日以降の計算値に着目したいと思います。  |
台風14号の進路予想が気になる方のために・・・・・
米軍台風進路予想(TC Warning Graphicをクリック。日本時間は+9時間)
http://www.usno.navy.mil/JTWC/
気象庁5日間予報
http://www.jma.go.jp/jp/typh/typh5.html
どちらの進路予想が正しい?ということではなくて、どちらかを主治医と考え、他方をセカンドオピニオンと考えて、安全マージンを考慮する使い方がイイと思います。
一応、気象庁は今夜までに熱帯低気圧になることを予想していますけれど・・・
さて、今日は今までとはちょっと異なった天気チェックの流れ(天気チェックの裏技)で書き進めていきたいと思います。
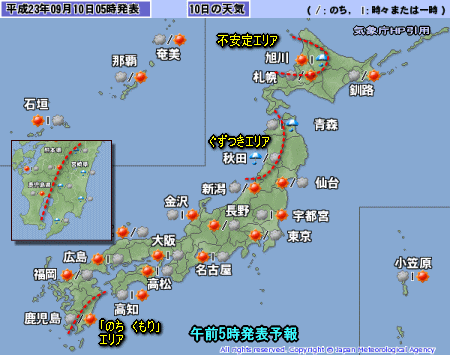
いきなり天気マークの天気予報から・・・・多くの方はこの図から天気チェックを始めるんじゃないかと思いますけれど・・・・
パッと見たところ、東北日本海側と北海道北部に傘マーク。
九州方面に傘マークはありませんから、台風の影響はナシね・・・なんて考えてしまうかもしれませんけど、拡大してみると宮崎周辺に傘マーク。
ネットの天気予報の中でも天気マークの数が多い気象庁HPの図でさえ、九州の雨が漏れています。
台風災害の紀伊半島にはマークがありませんから、この図の使い方も注意しなくてはなりませんよね。
(拡大が簡単にでき、全国の予報区分を表示できる気象庁HPの図がオススメです)
で・・・・予報官はこの図を作るにあたって、様々な天気図やシミュレーションを検討するわけですが、雨・・降水の範囲などを判断するにあたって多用されるのがMSMというシミュレーション。
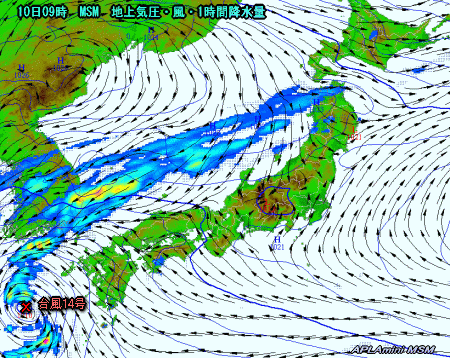
最寄りの県の予報官が、この図を見ながら「今日の天気予報をどう組み立てようか?」と考えていたのか、ちょっとイメージしてみてください。
そして、最寄りの地域の・・・・天気マークの天気予報の元ネタになる府県天気予報を読んでみましょう。
(天気マークの予報には「所により・・・」が表示されませんから、府県天気予報を読まないのは失敗のモト)
府県天気予報: http://www.imocwx.com/yohoud.htm
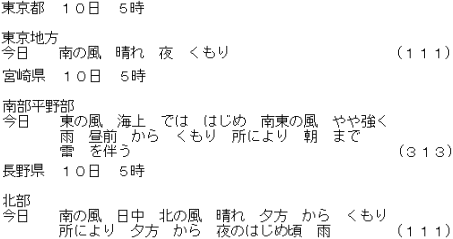
(予報の末尾にある3ケタの番号はテロップ番号といいます。(111)なら「晴のち曇」マーク、(313)なら「雨のち曇」マークを表示しなさいよ・・・という天気マークの予報の元ネタです)
東京の予報官・・・・今日いっぱい、東京に降水は計算されていませんし、上のアニメに書き込んだ雷雨が予想されるエリアからも遠いですから、日中は晴れの予報でイイな・・・・なんて考えて予報を作ったのかもしれません。
一方、宮崎の予報官は、台風が遠ざかって雨は止むな・・・晴れまでは回復しないんだろう・・・夜、再び降水エリアが東側に迫ってくるけど、雨の予報を入れる必要はあるかなぁ?・・・なんて夜の雨を迷いながら予報を作ったのかもしれません。
さて、予報官が予報を組み立てる場合、シミュレーションだけを見ているわけではありません。
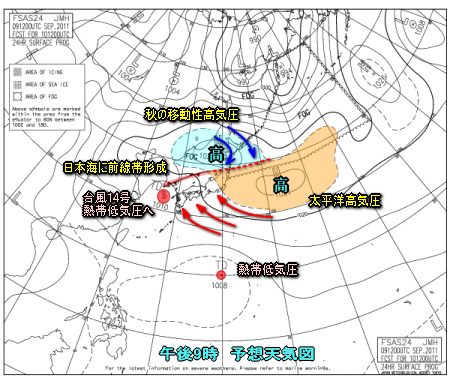
予報を組み立てる上で何を考える必要があるのか?・・・まずは超大ざっぱに気圧配置上のポイントを考えているはずです。
今朝は・・・台風14号の熱帯低気圧化と、日本海の前線、そこに吹き込む暖かく湿った空気(暖湿気)の様子・・・だと思います。
その上で、具体的には・・・・
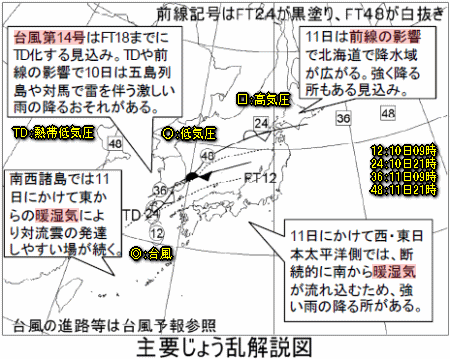
短期予報解説資料掲載の図ですけど・・・・ポイントは台風・前線・暖湿気・・・こんなことを考えていたんでしょう。
そして、まず台風の様子については・・・・・
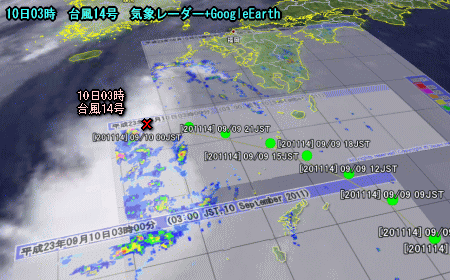
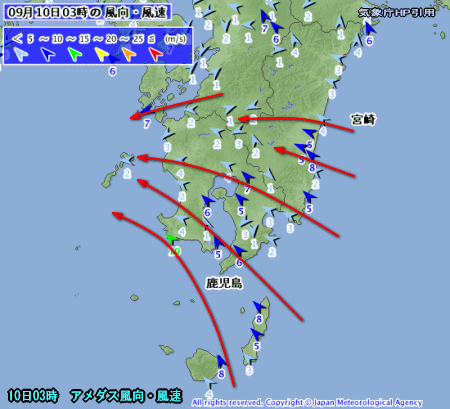
衛星やレーダー・アメダスなどを使って、台風周辺で何が起こっているのか?実況を把握して・・・・今の様子を可能な限り具体的にイメージしたはずです。

そして、シミュレーションと実況の対応を見ながら、雨が多く計算され過ぎているんじゃないの?なんて考えながら、予報を組み立てる前にシミュレーションを修正したかもしれません。
また、台風の今後の進路や、晴れのエリアがどのように変化するのか?を把握するために、上空の天気図を使って太平洋高気圧や偏西風の動向をイメージしたことでしょう。
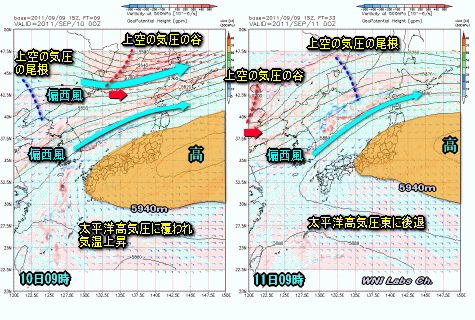
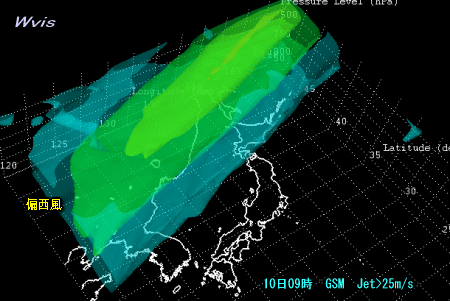
さらに、雨の原料になる暖かく湿った空気(暖湿気)の動向も詳しくイメージして、雨の計算値の修正の必要性や、シミュレーションの解像度では計算されない雷雨などの有無についても検討したかもしれません。
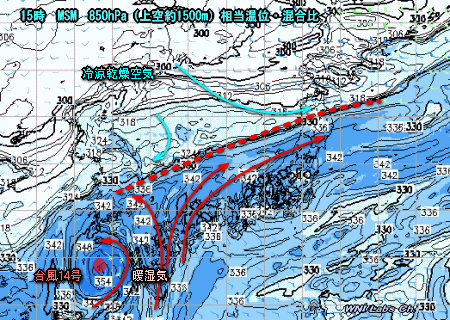
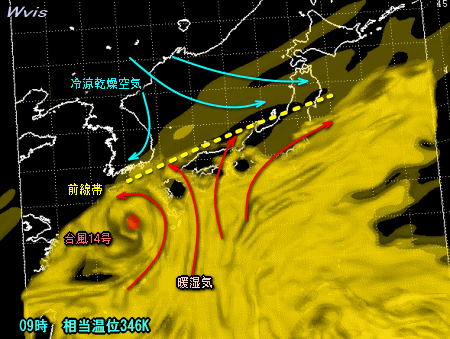
熟練の予報官の頭の中では、アニメのように立体的な暖湿気の動きがイメージされていたことでしょうね。
そして、前線の発達の程度を見るために、暖湿気と対になって前線を活発化させる前線北側の寒気もチェックしていたに違いありません。
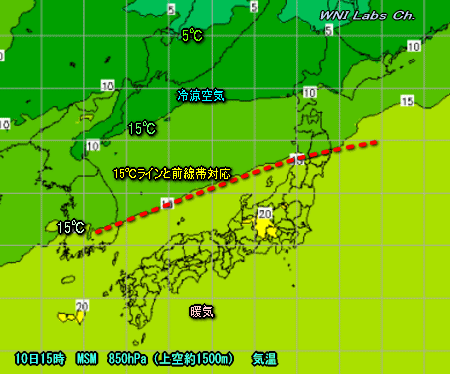
天気予報の最終製品といえる府県天気予報や天気マークの予報から予報官の思考過程を想像してみたわけですが、こう考えていくと、予報官が迷ったかもしれない箇所に気付くことがあります。
予報官が迷ったかもしれない箇所は・・・予報がアヤシイ場所で、選択しなかった天気予報のシナリオが予報がはずれた場合の天気になる可能性大。
このように考えておくと、登山やマリンスポーツなどで天気の急変に出くわしたときにも次善の策をとり易くなります。
実はコレ、気象庁の天気予報を解説する原稿を書くときのKasayanの天気チェック方法だったんです。
秋の行楽シーズン前の事故防止に・・・・天気に興味のある方はできる範囲で試してみてください。
なお、ここに掲載している天気図のほぼすべて、カタチこそ異なれどすべて無料で手に入れることができる情報です。
近々、天気図のリンク集も掲載したいと思っています!!
ご意見・ご質問等は、コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。
可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)
(当ブログはリンクフリーです)
2011年09月09日
台風14号の進路と週末の天気、そして暖湿流?(9月9日)
(「紀伊半島の大雨の本当の理由!!」・・・興味がある方は6日の記事をどうぞ)
台風14号の進路が気になる方も多いと思いますが、最新の観測値によって変更される進路予想図を、書きっぱなしのブログに掲載するのは不適切・・・というのがKasayanのポリシーなので、いつもリンクを掲載するにとどめています。
米軍台風進路予想(TC Warning Graphicをクリック。日本時間は+9時間)
http://www.usno.navy.mil/JTWC/
気象庁5日間予報
http://www.jma.go.jp/jp/typh/typh5.html
さて・・・台風12号のときもそうでしたが、天気予報で「暖かく湿った空気が流れ込んで」・・・・「大雨」「局地的に激しい雨」という解説が多いと思いませんか?
天気図に赤の矢印を描きこんで説明するヤツです・・・・・
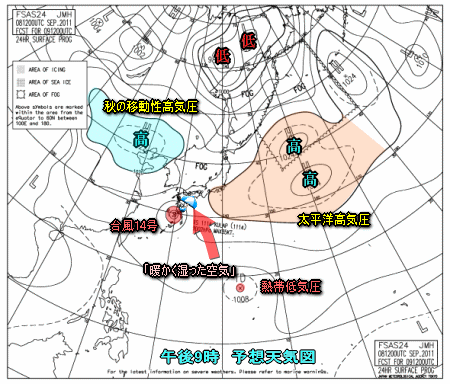
冬場の「寒気」「冬将軍」の図と双璧をなすお馴染みの図ですが、なんとなく「雨の原料」なんだな・・・というイメージで聞いておられると思います。
今日から週末にかけての天気予報の解説にも頻繁に登場してくるでしょうから、今日は「暖かく湿った空気」を中心に今日、そして週末の天気をチェックしてみたいと思います。
(長くなってしまったので、斜め読みしていただければOKです)
さて・・・「暖かく湿った空気」・・・相当温位という数値の高い空気のことですが、相当温位とは空気の湿り気と温度の両方を織り込んだ数値で、気温が高いほど、そして湿度が高いほど、大きな数字になります。
ですから、イメージどおり「雨の原料」の量の多さと考えてしまってもイイでしょう(空気の上昇のし易さなんかも判断できる数字です)。
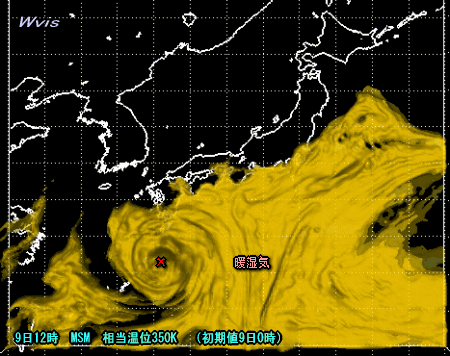
この図は今日お昼の図・・・・まずは「暖かく湿った空気」をリアルにイメージしていただこうと立体図を作っておきました。
相当温位が350K(ケルビン)という、雨の原料としては大きな数字の空気を立体的に表示したものですが、台風と太平洋高気圧周辺に多く存在しているのがわかると思います。
太平洋から蒸発する水蒸気が集まる場所・・・ですね。
これを数値として表現した専門の天気図がこれ(今朝3時)。
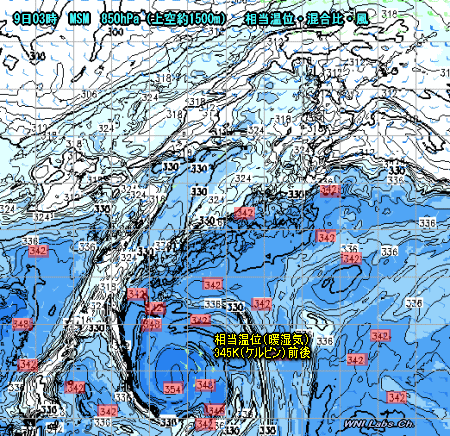
赤の数字が一般的に相当温位の数字としては高いところ・・・・雨の原料が多い場所ということになります。
青の色塗り部分は混合比といって空気に含まれる水蒸気の量をチェックするための数値を表現したものですが、水色が濃いところほど水蒸気が多い所。
衛星画像(水蒸気画像)でも、雨の原料の様子をチェックすることができます。

台風周辺や太平洋高気圧縁辺にあたる本州南岸、そして日本海に雨の原料が集まっていることがわかりますよね。
そして、雨の原料が流れ込んでくれば、雨が降り易くなる・・・ということも容易に想像できると思いますが、それに加えて、台風12号の大雨の解説にあったアレ・・・山にぶつかって上昇気流が発生すると雨雲ができる・・・という傾向があります。
また、乾燥した空気とぶつかったり(前線帯)、空気どうしがぶつかったり曲がって(シアーライン)上昇気流が発生しても同様。
そして、強い日差しに空気が暖められて発生する上昇気流・・・ゲリラ雷雨ですね。
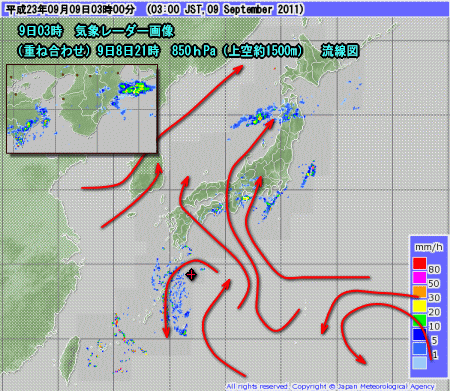
上の図と同じ今朝3時のレーダーに雨の原料の空気が流れ込む様子を矢印で書きこんでおきました。
東北日本海側にある雨雲の帯は冷涼で乾燥した空気とぶつかってできる雨雲。
紀伊半島付近や四国で発生している雨雲は山にぶつかってできる雨雲。
ちなみに、暖かく湿った空気の「流れ」は、こんな専門天気図などでチェックできます。
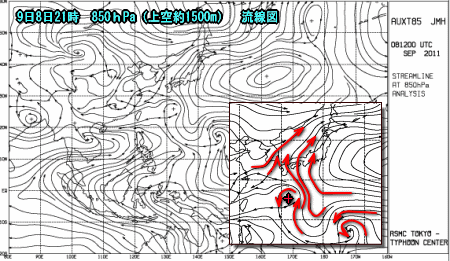
理科の授業みたいな「暖かく湿った空気」の話しはこのくらいにしておきましょう・・・・・
では、今日から週末の天気・・・・今朝の気象庁発表の天気概況に目を通しておきましょう。
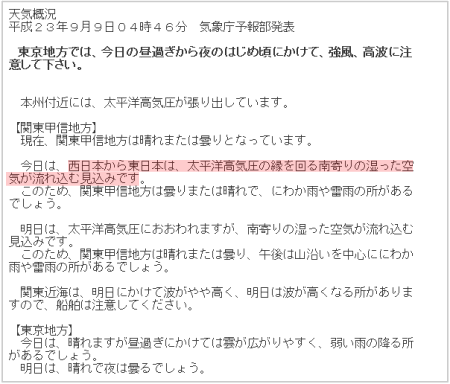
テレビの天気予報(今朝のYahoo天気の解説もそうでしたが)の解説と同じですよね(同じじゃなかったら困りますけど)。
また、短期予報解説資料というプロ用の資料にも・・・・

どうです?「暖かく湿った空気」=「暖湿気」について興味を持って読み進めることができました?
今日のポイントは、暖湿気による紀伊半島被災地と九州南部の雨と、北海道の雨。
紀伊半島や九州では山による上昇気流、北海道は空気が集まる(シアーライン)ことによる上昇気流に基づく雨ですね。
また、週末に関しては、暖湿気の流れ込みが日本海に拡大して山陰沖のシアーラインによる雨が活発になるようです。
文字だけじゃわかりにくいでしょうから、短期予報解説資料に掲載されている図も掲載しておきましょう。
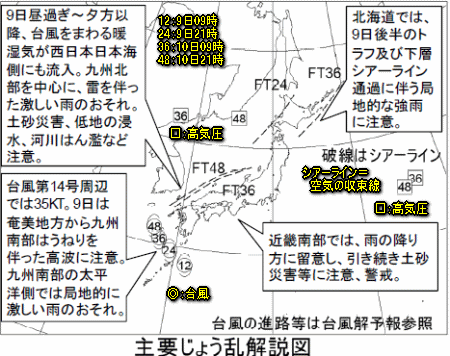
上の文字情報と照らし合わせて読んでいただければ・・・・なんとなくわかりますよね?
ちなみに北日本に影響する「トラフ」は、上空の気圧の谷のこと。
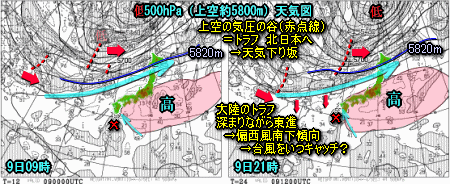
反時計回りの低気圧性の空気の流れを作る悪天の原因と思えばOKです。
では・・・・ようやく今日の詳しい雨や風の様子。
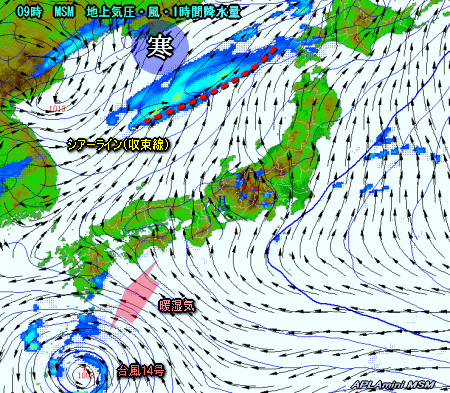
「暖かく湿った空気」が矢印に沿って流れ込み、どこで上昇気流が発生して雨が降るか?ということを考えながらチェックしていただければ、いつもより深読みができるかも?
続いて週末の雨の様子・・・・「暖かく湿った空気」が流れ込む様子のアニメも併せてチェックしてみてください。
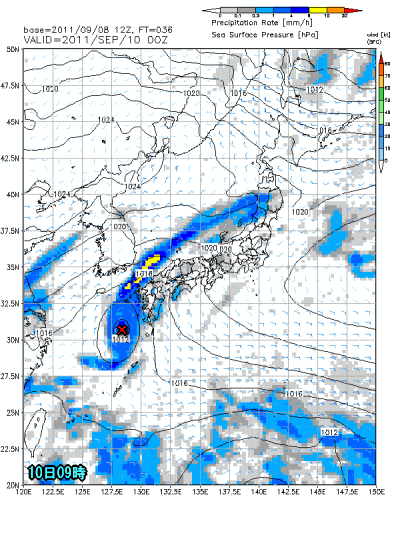
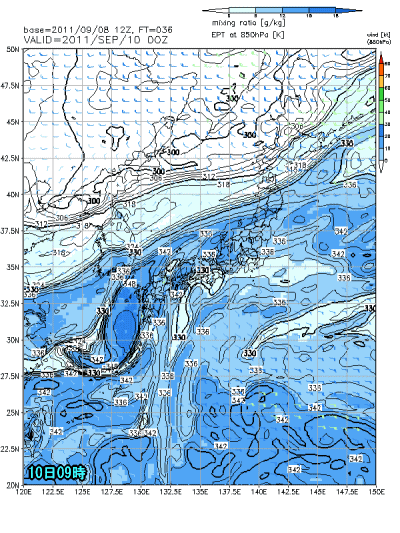
雨と「暖かく湿った空気」の関係を意識してチェックできました?
ムシムシした・・ちょっと不安定な天気の週末になりそうですね。
ご意見・ご質問等は、コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。
可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)
(当ブログはリンクフリーです)
2011年09月08日
台風14号進路予想と紀伊半島被災地の雨(9月8日)
(「紀伊半島の大雨の本当の理由!!」・・・興味がある方は一昨日の記事をどうぞ)
台風14号が発生してしまいました。
一昨日夜、そして昨日朝の計算値では発達がまったく計算されておらず、気象庁発表の明後日の予想天気図(気象庁HPで見ることができますよ)では消滅させていましたから、予報官も衛星画像で雲のカタマリが出来る様子を見て「ありゃりゃぁ!」という状態だったと想像しています。
台風の発生によって、しばらくは晴天が続くと思われた今後の天気も変化する傾向。
台風の進路予想は最新の進路予想図でチェックしていただくとして、このブログでは「台風14号で何が起こるのか?」を中心にまとめておくことにします。
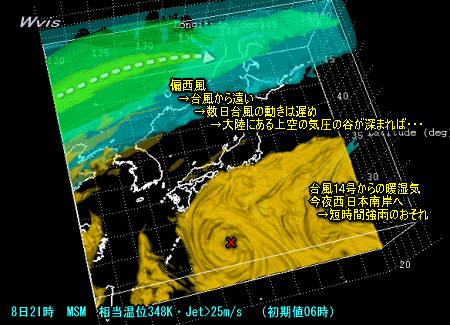
米軍台風進路予想(TC Warning Graphicをクリック。日本時間は+9時間)
http://www.usno.navy.mil/JTWC/
気象庁5日間予報
http://www.jma.go.jp/jp/typh/typh5.html
それでも一応、台風進路予想図とは別に、気象庁の通常の天気予報の基礎資料となるGSMモデルというシミュレーションデータは確認しておきましょう。
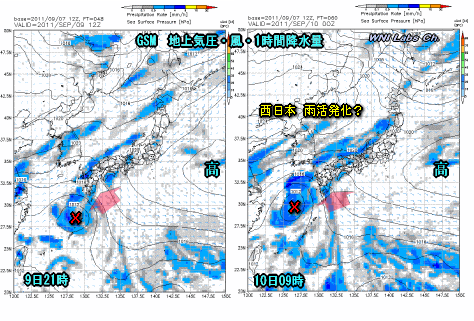
リンク先でチェックしていただいた進路予想図とほぼ同じだと思います。
ついでに、アメリカのGFSモデルというシミュレーションも見ちゃいますか・・・・
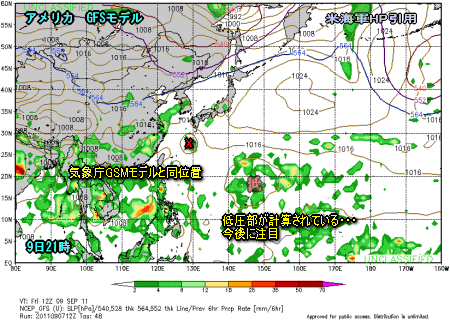
こちらも、ほぼ同様。
発達の程度については断言はできませんが、進路については劇的な変化という可能性は低いのでは?
| 17時45分追記 最新の計算値(8日12時初期値)ですが・・・・台風のコースは今朝の計算値とほぼ同じかやや北寄り。 そして速度は若干早まる傾向。  今夜は暖湿気が流れ込む西日本南岸でまとまった雨になる恐れがありますが、明日は九州東岸で大雨。 地上に近い上空約1500mの寒気の様子も重ねておきましたが・・・暖かく湿った空気が流れ込む日本海では寒気との間に前線帯ができ、雲の帯が発生します・・・こちらの影響は今後の台風の進路次第・・・要チェック項目です。  それほど発達していない台風といえども九州にかなり近づいて通過するので、台風を押し流す上空の流れ。 太平洋高気圧の微妙な張り出し次第でもう少し北寄りになる可能性もありそうですから・・・・ありきたりですけど、最新の進路予想図でアップデートが必要です。 |
では今日の天気・・・・台風進路との流れもありますから・・・・今日はもったいぶらずに?真っ先に今日の雨と風のシミュレーションからチェックしていきましょう。
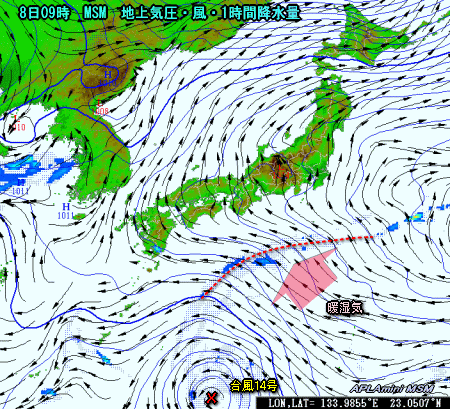
アニメを見ていただければコメントは不要でしょう。
繰り返しになりますが、所詮シミュレーションデータですから、台風がギリギリかすめるとか、雨は頭上にかかっていない、などと細かなことにこだわって見るのは誤った使い方。
あくまで天気変化の傾向を知る手掛かりとしてチェックして、予報官がこの図を修正したり安全マージンを考慮して作った天気予報の最終製品・・・府県天気予報を深読みするための(確からしさを把握するための)道具として使ってください。
府県天気予報: http://www.imocwx.com/yohoud.htm
上のアニメには、赤矢印で暖湿気、青矢印で寒気の様子を書き込みしておきましたから、暖湿気が西日本南岸に流れ込んで雨が降る・・・というメカニズムは直感的にご理解いただけるかと思います。
でも、直感的じゃどうしようもないので、予想天気図で詳しくチェックしておきましょう。
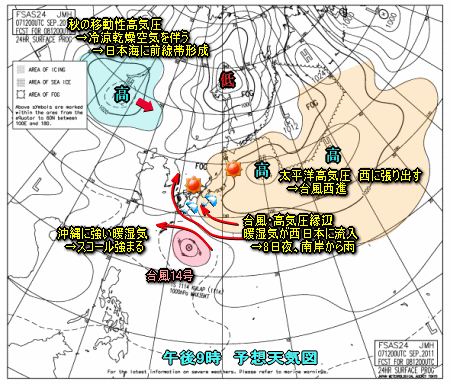
こちらも書き込みをしておいたので、読んでいただければ・・・・・・
今朝発表された短期予報解説資料というプロ用の資料の解説がとても簡単に書かれていたので、続いてこれも読んでおきましょう。
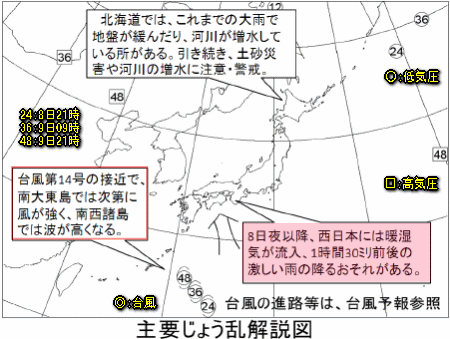
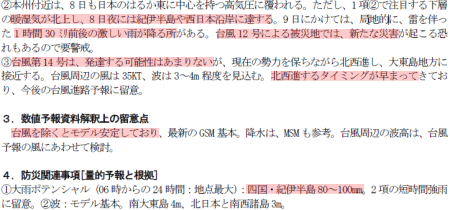
「台風14号で何が起こるのか?」で、一番懸念されるのが、紀伊半島など台風12号の被災地で雨が降るということ。
台風12号では、暖湿気の流れ込みによって、台風接近前に1000キロ以上も離れた関東で大雨になりましたが、今夜から予想されている西日本南岸の雨も規模は違えど同様の現象だからです。
問題の暖湿気の流れ込みの様子を詳しくチェックしておきましょう。

赤く色塗りしてある数字が強い暖湿気(暖かく湿った空気)のエリア。
台風12号と同様、太平洋高気圧縁辺の南風が手助けして、台風の東側から北上してきます。
そして、今夜には西日本南岸に到達・・・大気が不安定になって短時間の強雨が予想されているわけです。
ところで・・・・基本的に今日日中は、太平洋高気圧の覆われて乾いた晴天になりますから、テレビの天気予報では「今日も乾燥した爽やかな晴天になるでしょう」というようなコメントから始まると思います。
でも、西日本の方は、ここで注意をそらしてはダメ。
「ただ」・・・で始まるはずの西日本南岸の雨に関するコメントを聞き忘れないようにしてください。
(「ただ」以下のコメントをしなかったお天気キャスターは即刻レッドカードです)
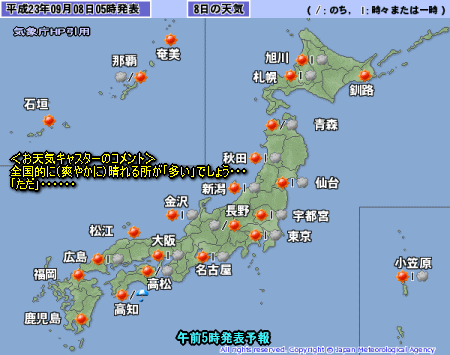
これは気象庁HPに掲載されている天気マークの天気予報(上でリンクした府県天気予報を簡略化しただけ。「所により」は読みとることができないので、府県天気予報をチェックする前に天気分布を読みとるために使うのが正しい使い方)。
パッと見ただけでは西日本南岸の今夜の雨はイメージしにくいと思います。
ましてや、昨夜発表の予報では傘マークは全く表示されていませんでしたから、この図だけで天気を判断してはいけません。
(たぶん、昨夜の府県天気予報の中で「所により夜遅く雨」程度の予報だったと思います)
お天気キャスターのコメントが重要になってくる場面ですね・・・・・
西日本を拡大すると・・・・
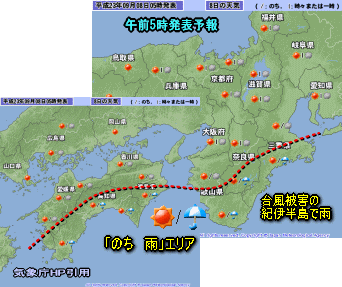
ようやく西日本南岸の「のち 雨」の予報が見えてきました。
インターネットの天気予報では多くの場合、気象庁HPよりずっとデフォルメ、簡略化された図が掲載されていることが多いですから、天気マークの天気予報についても、地域拡大も簡単にできる気象庁HPを使うことをおすすめします。
ついでですから、天気予報のチェック方法についても・・・・
民間気象会社(日本気象協会も民間なんですよ)が発表しているピンポイント予報は、天気分布を天気マークの天気予報で概観し、府県天気予報をチェックした後、さらに詳細な天気傾向を知るために使うのが正しい使い方。
なぜなら、お隣のピンポイントエリアに雨マークがついていても、頭上のピンポイントエリアにはギリギリ雨マークが表示されないということもあるので、安全マージンをとることができないから。
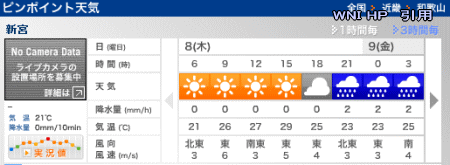
天気マークの天気予報⇒府県天気予報⇒ピンポイント予報、という流れが正しい天気予報の使い方ですから、この機会に覚えておいてくださいね。
ちなみに、民間気象会社のピンポイントではないエリアの予報については・・・・気象庁発表の予報のセカンドオピニオンとして使うのが吉。
どちらの予報が当たる・・・だから××の予報しか見ない・・・という使い方は、正しい天気判断のチャンスを自ら放棄しているといってよいでしょう。

で・・・このブログの使い方?・・・以上のチェックをする前、あるいは後に、天気予報の安全マージンを考える資料にしていただければ・・・・・と思います。
ご意見・ご質問等は、コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。
可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)
(当ブログはリンクフリーです)
2011年09月07日
広く乾燥した晴天、北日本日本海側不安定(9月7日)
(紀伊半島の大雨の本当の理由!・・・興味がある方は昨日の記事をどうぞ)
| 16時20分追記あり 20時50分追記あり |

台風12、13号も天気図から消え、北海道の大雨も峠を越し・・・今日のブログはのんびりとさせていただきたいなぁ・・・と。
いつもと違って(同じ?)、Kasayanがのんびりと天気チェックした流れに沿って書き進めていきたいと思います。
チェックした天気図全部は掲載できませんが、こんな天気チェックの流れもあるんだなぁ・・・・と思って興味のある図だけ目を通していただければ結構です。
さて、窓を少し開けて寝たんですけど、寒くなって午前3時に目を覚ましてしまいました。
目がさえてしまったので、PCのスイッチオン・・・・3時のアメダスを見るとKasayanの住む長野市内は14℃。
車で45分ほどの菅平は6.8℃・・・・東京では冬の気温・・・朝にかけてまだまだ下がりそう・・・・
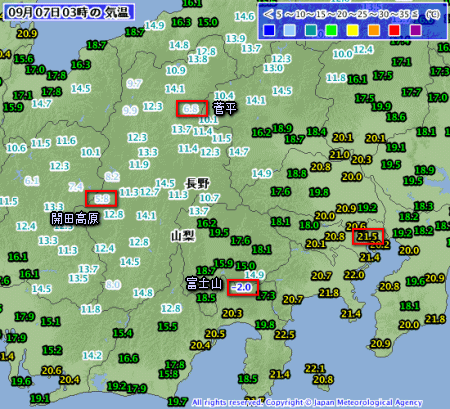
静岡県方面を見ると、富士山頂で-2.0℃。
少なくとも朝に関しては秋の気配を実感。
富士山で氷点下だから、上空に寒気が入っているんだろうなぁ・・・・富士山頂よりちょっと低いけど上空3000m付近の実況天気図を確認してみようかな・・・・・と・・・・・
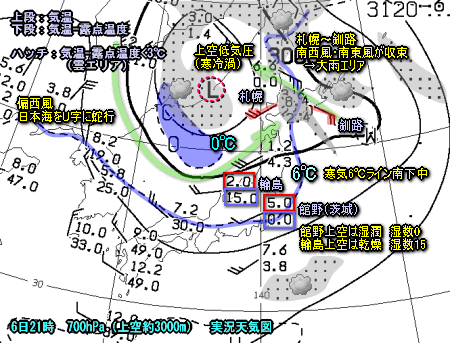
手に入る直近の実況天気図は昨夜21時の天気図。
大陸沿岸、ウラジオストクあたりに上空の低気圧があって、低気圧の回りを反時計回りに強い風(偏西風)。
低気圧の南西側には0℃の寒気のカタマリがあって、どうやら北西の強い風が大陸の寒気を運んできているようですね・・っと。
せっかくだから絵にしておこうか・・・・寒気の様子や曇りのエリアを作画ソフトでゴソゴソと書き込んで・・・・・
衛星画像ではどう見えるのかしらん?
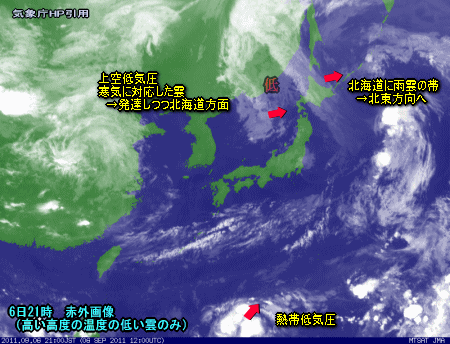
実況天気図の曇りエリアは、気温と露点温度(空気中の水蒸気が粒になる温度)の差が3℃未満の場所なんだけど、衛星画像とピッタリ(当たり前ですけど・・・)・・・・・フムフム・・・・
水蒸気つながりで・・・北海道に大雨を降らせた雨の原料・・・水蒸気の流れもチェックしておこう・・・・
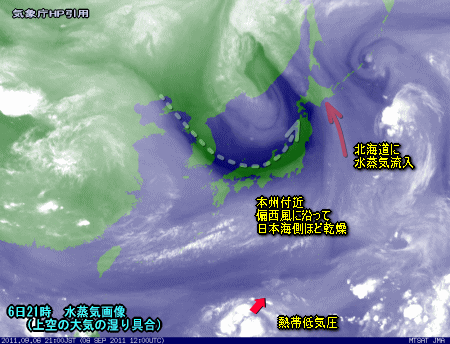
水蒸気画像にも書き込みを・・・・・
北海道に集中的に水蒸気が流れ込む半面、日本海側からは乾燥した空気が流れ込んでいるんだから、雨雲も発達するわけですなぁ・・・・
雲の下ではどうなっているの?
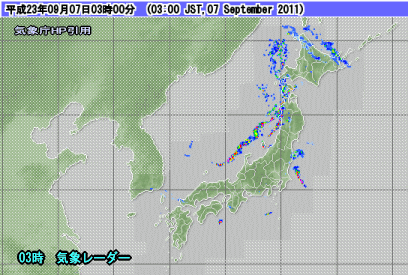
北海道の雨はおさまりつつあるけど、北海道・東北日本海側じゃ結構激しいスコールになっているみたい。
山陰方面まで帯状になっているのは、さっき見た実況天気図の-3℃前後の寒気と対応していそう・・・
上空の寒気に伴う不安定な降水ってヤツですな・・・
実況把握はまあこんなもんでイイでしょう・・・・とりあえずお茶でも飲んで、本でも読みますか・・・・・
さて・・・・本もつまらんし、ラジオもつまらんから・・・・今日日中はどうなるのよ?・・・上空から下へとチェックしていきますか・・・・・・
上空5700m付近の気圧の谷も、上で見た上空3000mと大体同じだけど・・・・大気不安定の目安になる上空5700m付近の寒気は・・・
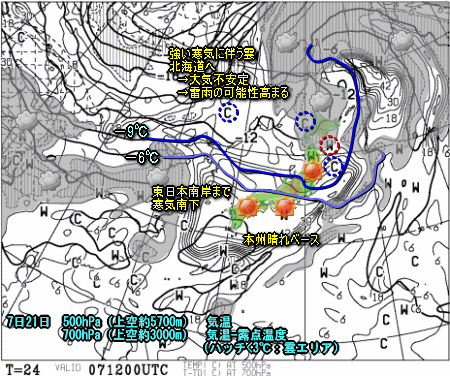
東日本は-9℃の寒気にすっぽり・・・北日本には-12℃の寒気がやってきて、北海道の西側にC(コールド)スタンプがあるから、寒気の小さなカタマリが北海道へドスン・・・・
こりゃ不安定な天気になりそうだぞと・・・・昨日までの雨があるから・・・引き続き警戒ですねぇ・・・
寒気を見たついでに、今夜の雲の様子も・・・・実況天気図と同様、気温-露点温度<3℃のエリア・・・ちょっと広めに塗ると曇りのイメージのエリア。
北海道じゃ晴れないね・・・だけどそれ以外は晴れそうですな。
晴れるのはイイけど、寒気も南下しているから本州では夕立があるんじゃないの?
地上に近い上空約1500mの気温もチェックしておきますか・・・・・
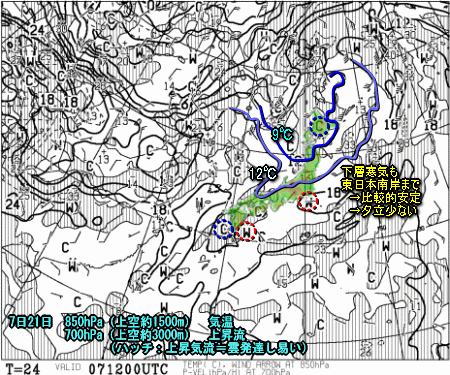
地上付近にもそこそこ寒気が入ってきてるジャン・・・・そりゃ寒さで目が覚めたんだから・・・・
大気は安定傾向だから夕立はなさそう・・・でも、一応不安定の原因・・・暖湿気の様子もチェックしておこう。
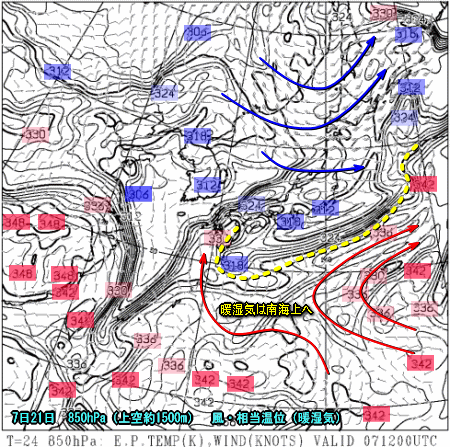
暖湿気は南岸まで・・・全国的に乾燥冷涼な空気に覆われる・・・・・・「気温は上がっても過ごしやすい」っていうコメントをお天気キャスターがするパターンね。
で・・・北日本の雨は?
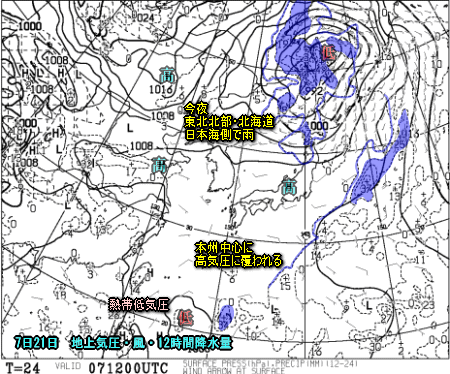
日本海側中心ね・・・・・
熱帯低気圧・・・発達しそうもないな・・・追跡は必要だけど・・・・・
疲れちゃったから、MSM(別のシミュレーション)で具体的な雨の変化をチェックしちゃえ・・・・
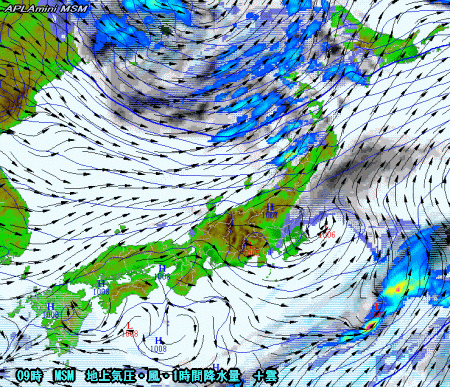
うんうん・・・・先のチェックどおりね・・・・・・
・・・・・以上で、Kasayanの今朝の行き当たりばったりのチェックの流れは終わりにします。
でも、これだけじゃあんまりなので、今夜の予想図にザックと解説をまとめておくことにします。
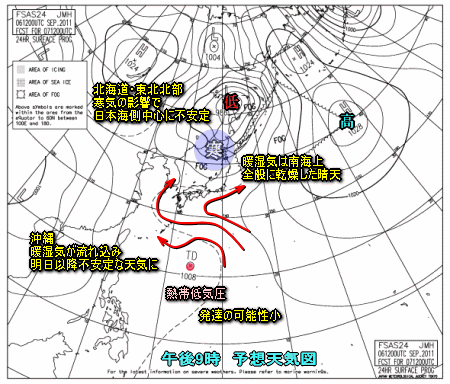
| 16時20分追記 あらららら・・・・13時05分、気象庁が台風14号を観測したと発表。計算値と衛星画像で見る限り、今日中に台風14号まで発達するとは思わなかったんですが・・・・これぞゲリラ台風ですね。時間があれば、今後の計算値など夜に追記してみたいと思います。 (最新のMSMシミュレーションでも台風の目安風速17.2m/sギリギリ。台風情報でも明日15時・・・10日15時でもようやく20m/sの予想・・・。熱帯低気圧に限りなく近い台風14号ですが、雲のまとまりはそれなりに台風のカタチ。どうなるのか?軽々しい判断はできませんけど・・・・。問題は明後日あたりから暖湿気が太平洋岸に流れ込んで、災害の地にイタズラをすること。この点は要注意だと思います。  |
| 20時50分追記 気象庁台風進路予想図及びGSMモデル、ならびにアメリカGFSモデルを比較しても・・・・発達、速度については不明です。 ただし、沖縄方面へと進む確率は高いと思われます。    |
ご意見・ご質問等は、コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。
可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)
(当ブログはリンクフリーです)
2011年09月06日
台風13号と北海道の大雨、紀伊半島大雨検証(9月6日)
昨日のニュースなどで解説されていた紀伊半島の大雨の原因・・・・どうも腑に落ちなくて様々考えていたのですが・・・・昨夜ゴソゴソとデータをまとめていたら、ちょっとした結果が出てしまいました。
今日は北日本の大雨をチェックする必要があるのですが、紀伊半島の大雨の原因を生かすことができるかもしれない?ので、まずは「紀伊半島の大雨・・本当の理由!」と題して(週刊誌みたいなタイトルですね)、まとめた結果をご紹介しておきます。
1、紀伊半島の大雨・・・・本当の理由!!
台風12号に伴う紀伊半島の大雨の原因について、天気予報やニュースのどの番組でも、「暖かく湿った空気が紀伊山地南東部にぶつかって上層気流を作り激しい雨になった」、さらに「台風がゆっくりと進だため激しい雨が降り続いた」と解説されています。
確かに紀伊半島南東部を中心に降水量は多くなっていますし、長時間雨が降り続きました。
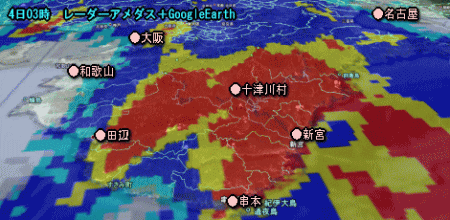
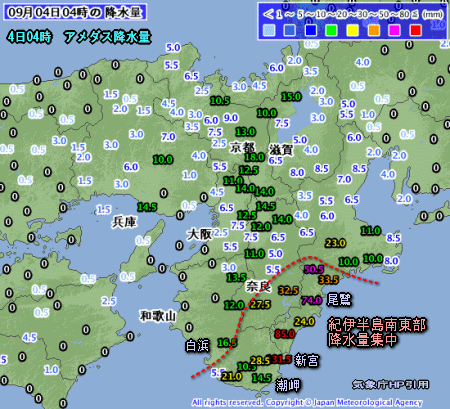
でも・・・・本当に理由はそれだけでしょうか?
台風がゆっくりと進んだため強雨が続き、台風の四国上陸によって台風本体の雨雲の影響も加わったことは容易に想像できますし、解説としては正しいと思います。
ただ、3日夜から4日未明にかけて被害が集中しているようですし、被災者のインタビューなどを聞いていると「夜中に屋根に穴が開くような強い雨が降った」というような話を耳にします。
アメダスの降水量と風向の観測値を時系列で見てみましょう。
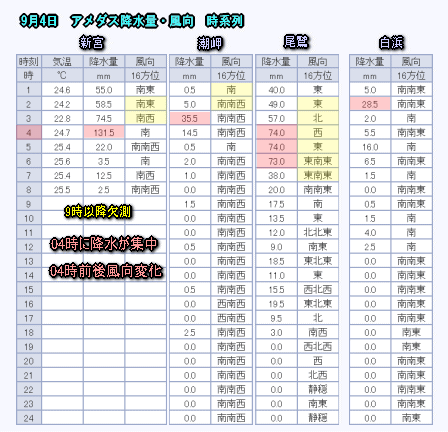
紀伊半島のアメダスでは午前3時~4時に、降水量が前後の時間の2倍~7倍も増え、短時間に風向が変化しています。
大雨が続くと土砂災害が発生しやすくなるのは当然ですが、紀伊半島のようにもともと降水量が多いところでは排水能力も高くなっていると思われますから、それだけで短時間に多数の場所で災害が発生するとは思えません。
そこで、大雨が続いて限界状態にあった降水と排水の均衡を打ち破る大雨が短時間に降り、災害の引き金を引いてしまったとは考えられないでしょうか?
そうだとしたら、降水と排水能力の均衡を打ち破る短時間の大雨がどのようなメカニズムで降ったのか?が、今回の紀伊半島の災害の原因の本質であり、今後の防災上の資料になると思われます。
少々興味深い資料がまとまったのでご紹介します。
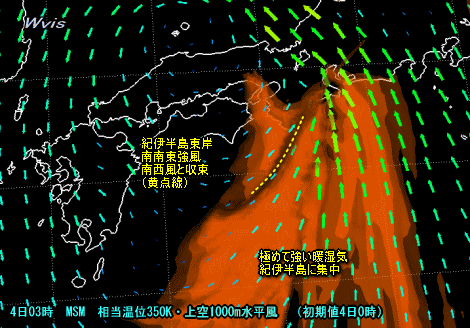
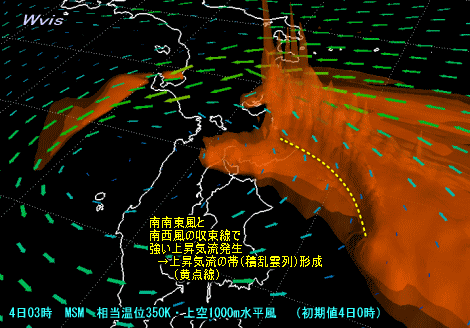
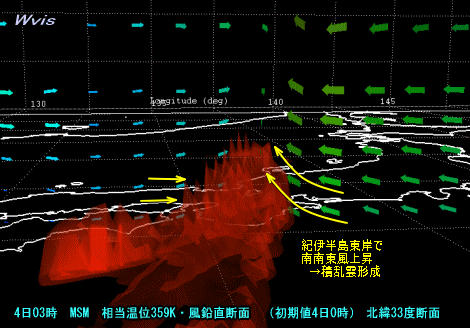
4日03時の暖かく湿った空気(雨の原料:以下暖湿気と呼ぶ)と上空1000m付近の風の様子を、MSMというシミュレーションデータで立体的に表現したものです。
紀伊半島の東側に南南東方向から強い暖湿気が流れ込んでいますが、他方、西側から西~南西の風が吹きこんで、急激に風向が変化する場所が形成されています(上段の図の黄色の点線)。
いわゆる収束線(シアーライン)と呼ばれ、空気の流れが集中して上昇気流が発生する線状の場所といえますが、その場所であたかも壁のように暖湿気が上昇していることがわかります(中段の立体図と下段の断面図)。
すなわち、収束線に沿ってライン状に積乱雲が発達していたことが想定され、収束線の形成とともに急激に降水量が増大したこと、そして通過とともに急激に降水量が減少したことが説明できます。
また、収束線の通過に伴い風向が急激に西寄りに変化したことも説明できます。
風向について実際の観測値も、以下の結果を示しており、収束線が形成されていたことを示唆しています。
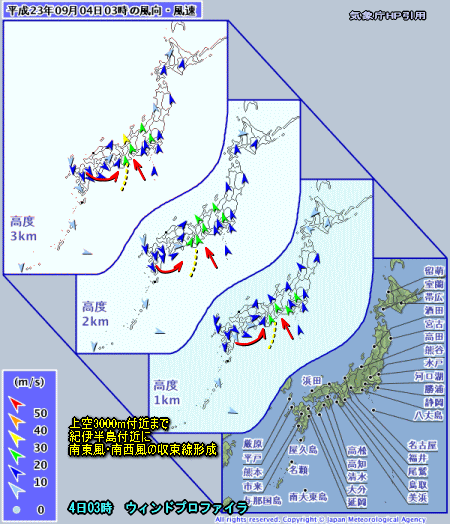
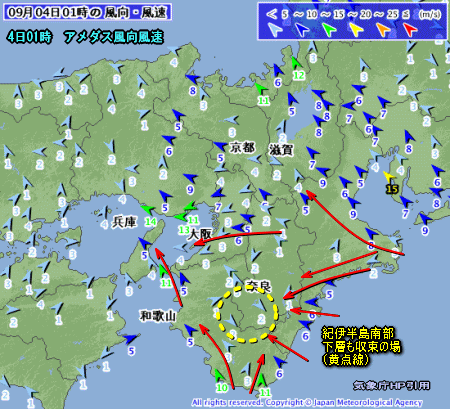
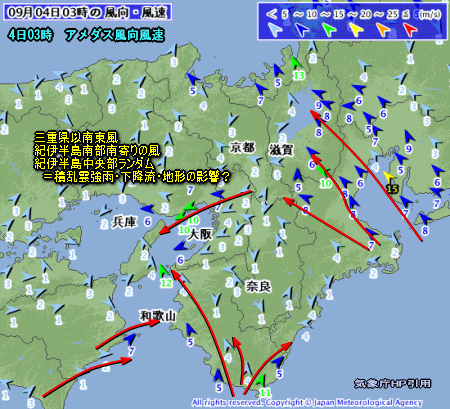
ウィンドプロファイラによる上空の風向は明らかに収束線の形成を示しており、地形の影響や発達した積乱雲からの下降流の影響を受けやすい地上のアメダスにおいても、大雨の前(午前1時)に収束の場が読みとれます。
以上ですが、説得力があったでしょうか?
もちろん、紀伊山地の地形が上昇気流の形成に大きな役割を果たしたことは確かだと思いますが、急激な降水量の増大はそれだけで説明するのは困難です。
ニュース等で解説されていた原因に加えて、収束線の形成と通過の両方が今回の大雨の原因として考えられるのではないでしょうか?
大雨が続いた後に、限界を超える短時間の強雨。
この組み合わせのタイミングを探ることが今後の防災に役立つのでは?と考えた次第です。
2、今日の天気
北海道では昨日から大雨が続いています。
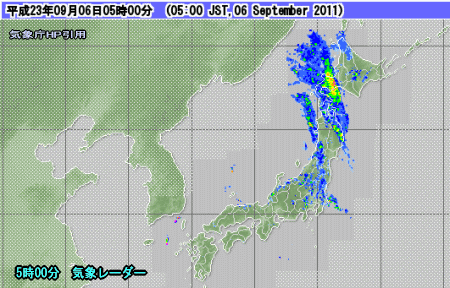
なんでこんな帯状の雨が降るのか?気圧配置から・・・・
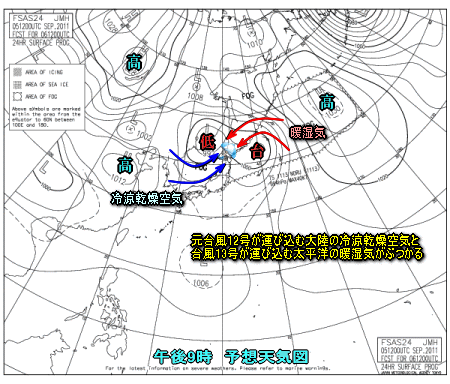
台風13号を回る暖かく湿った空気(暖湿気)が、午前中は北海道東部から、台風が北上する午後には北海道北東部から流れ込み、元台風12号が運び込む大陸の涼しい空気とぶつかって雨雲が発達するというメカニズム。
同じ所で大雨が降り続く・・・という、一昨日あたりどこかで聞いたような現象が起こるので、ニュースではトップ項目、天気予報では警戒が呼びかけられています。
短期予報解説資料というプロ用の資料でもうちょっと詳しく見ると・・・・
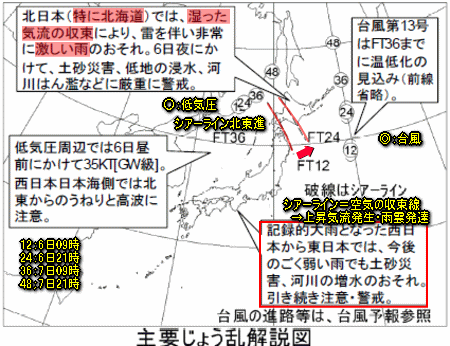
暖湿気と涼しい空気がぶつかる場所・・・シアーラインと表現されています。
今夜にかけて少しずつ北東に進むようです。
では、暖湿気の様子を詳しくチェックしてみましょう。
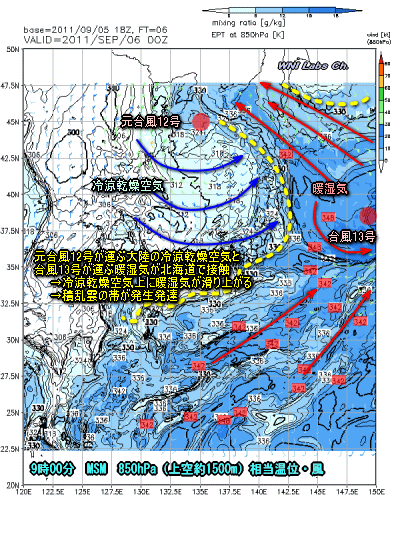
水色に塗られた湿り気をたくさん含んだ空気と乾燥した空気が黄色の線付近で接触し、北海道付近でぶつかる様子がわかると思います。
もうちょっとリアルに・・・・
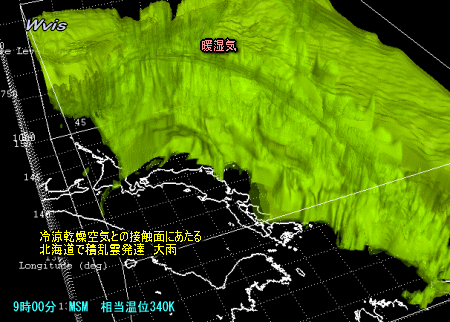
本州方面の暖湿気は南岸まで下がっていますが、台風13号に近い北海道には陸地まで流れ込む様子がわかるりますよね。
あと・・・いきなりですが・・上空の寒気もチェックしておきます。
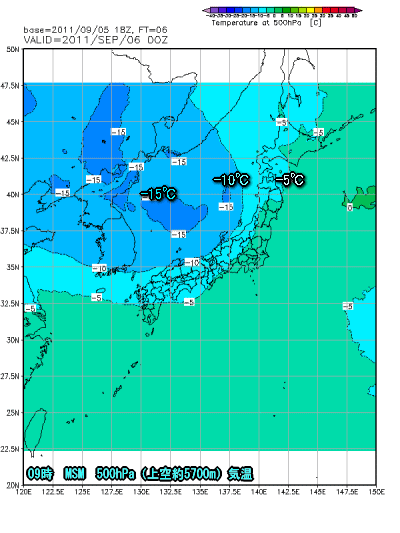
冷涼乾燥空気が南下しているということは、上空に寒気が流れ込んでいるわけで・・・寒気が流れ込めば本州でも大気が不安定になる場所・・・夕立が発生する場所が考えられるからです。
夜には-10℃の寒気が南下してきますから、そこそこ不安定な所も出てくるんじゃないでしょうか?
ということで、北海道の大雨と、夕立が発生する場所を気にしながら具体的な雨の様子をチェック。
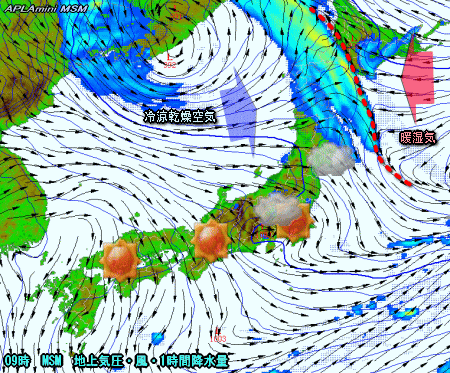
見ていただければわかりすよね・・・・北海道の大雨は一目瞭然・・・関東付近の夕立がちょっとアヤシイ。
最後にオマケ・・・・寒気をもたらしたり、台風13号を北上させている上空の気圧の谷と偏西風の様子を掲載しておきます。
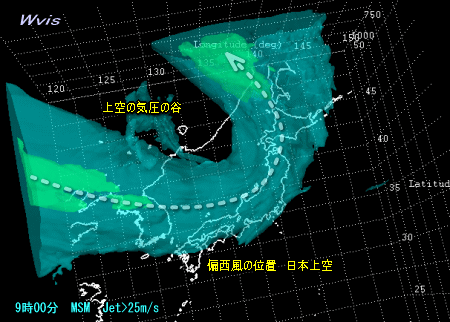
ご意見・ご質問等は、コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。
可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)
(当ブログはリンクフリーです)
2011年09月05日
台風12号・台風13号の動向、今日まで残る影響(9月5日)
| 12時25分追記、 20時20分追記 |
台風12号の影響がおさまらないうちに台風13号が発生。
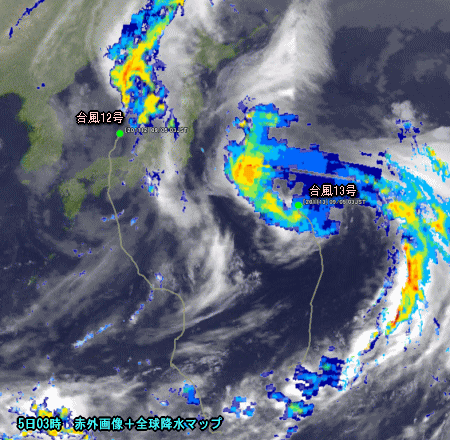
台風13号の進路を含めて今後の空模様が気になる方も多いと思いますが、テレビと同じ順番では芸がないので?、まずは向こう一週間の天気傾向からザクッと見ておきましょう。

7日から6日間は太平洋高気圧に覆われて晴れが続きそう。
ノロノロ台風12号の影響が続きましたからヤレヤレと言ったところですが・・・晴れたら暑くなるんじゃ?
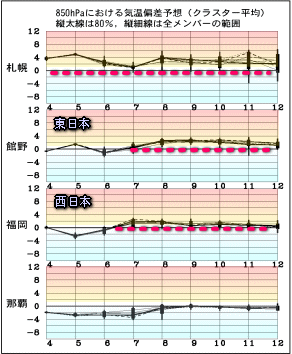
想像どおり、7日以降は平年を上回る気温が予想されています。
もっとも、さすがに9月ですから、朝の気温は低め。
朝と日中の温度差が10℃近くもありそうですから、寝苦しさはないでしょうけど・・・・・・・
さて、テレビの天気予報では今日もそれなりに警戒モードの放送がされているんじゃないかと思います。
台風に先行して東日本で大雨がありましたけど、台風が去るにあたっても最後は東日本の雨で締めくくられるようです。
では、目先の台風12号と台風13号の影響について詳しくチェックしていきましょう。
まずは、予想天気図から・・・と言いたいところですが、二つの台風が目立っているだけで気圧配置の時系列的な流れがわかりにくいので、短期予報解説資料というプロ用の資料に掲載されている図を抜粋しておきました。
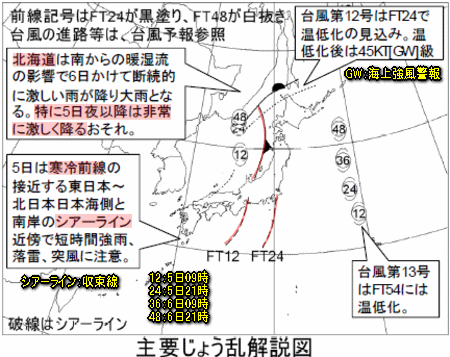
台風13号・・・北海道に接近しますが、とりあえず上陸の心配はなさそう。
ただ、北海道・・・道東方面は台風から流れ込む暖湿気の影響で非常に激しい雨が予想されています。理屈だけでいえば先の紀伊半島と同じ現象ですけど・・・。
他方、台風12号がらみでは、台風12号の温帯低気圧化にともなって発生した寒冷前線が、東日本日本海側を通過。
さらに太平洋側には風が収束して(雷雲を発生させる)上昇気流が発生しやすい場所・・・シアーラインが発生して東海~関東を通過。
東日本中心に比較的短時間ではあるものの、ゲリラ雷雨の時に発生するような激しい雨の降り易い状態・・・ということが予想されています。
米軍台風進路予想(TC Warning Graphicをクリック。日本時間は+9時間)
http://www.usno.navy.mil/JTWC/
気象庁5日間予報
http://www.jma.go.jp/jp/typh/typh5.html
では、気になる台風13号・・・進路を決定する上空の偏西風の様子からチェックしておきましょう。
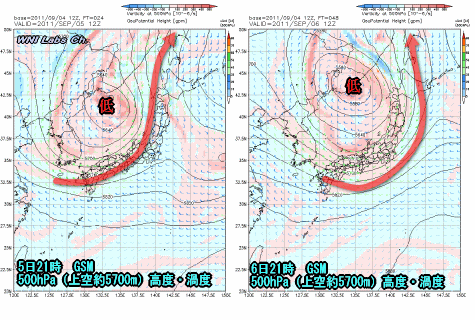
しばしば天気予報で耳にする上空の気圧の谷が発達して上空の低気圧になっています。
上空の低気圧の南端を流れる強い風が偏西風・・・上空の低気圧が発達して偏西風が三陸沖へ・・・台風13号をキャッチして、北海道に上陸する前に北へと押し流してしまいそう。
これを地上の気圧配置と降水の様子で見ると・・・・
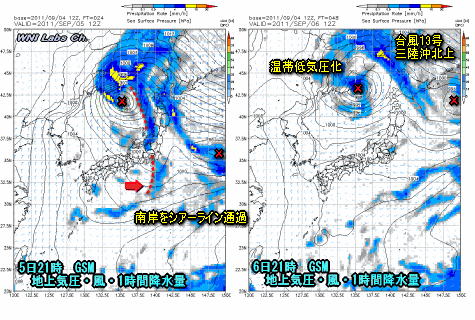
上陸はなさそうなので一安心というところですけど、台風の北側の東風が暖湿気を北海道に運び込み道東で大雨の恐れ。
ついでに本州付近を見ておくと・・・今日は寒冷前線とシアーラインの雨の帯が通過して・・・明日は回復ということのようです。
ということで・・・次は寒冷前線の発生の様子をチェックしておきましょう。
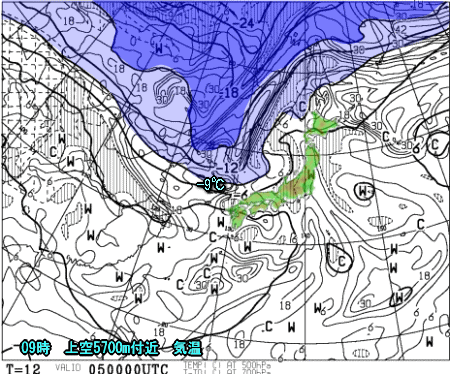
台風12号が大陸の寒気を引きづり下ろしてきます。
このため、台風が運び込んだ暖かく湿った空気と寒気がぶつかって日本海に寒冷前線が発生。
北陸から東北の日本海側では、寒気の南下とともに前線の雨が活発化します。
そして、南岸のシアーラインもチェック。
シアーラインは風が集まったり急激に風向が変化することによって上昇気流が発生しやすい場所・・・詳しい雨の様子と一緒にチェックしてしまいましょう。
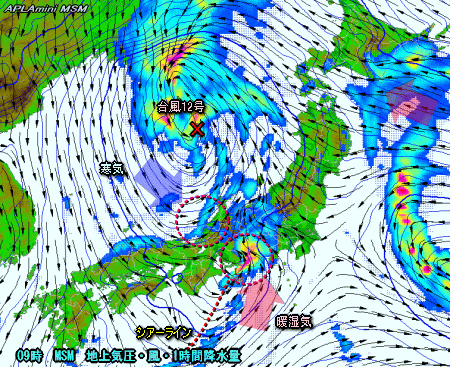
暖気と寒気を矢印で書きこみ、大雨の注意ポイントを赤丸で囲みました。
南岸の風の流れ・・・北西風が急激に南西風に曲がっている場所がシアーライン。
シアーラインの東側に暖湿気が流れ込んで雨雲が活発になることがわかります。
暖湿気をもっとリアルにしてみると・・・・
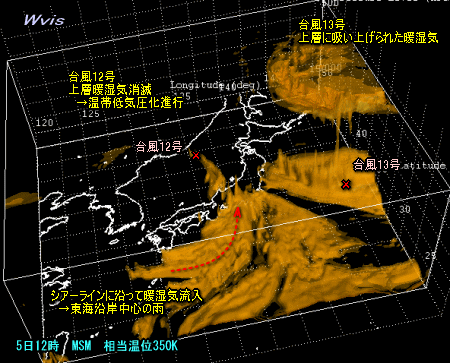
紀伊半島に大雨を降らせ続けた強い暖湿気・・・紀伊半島の東側に抜けて、今日はシアーラインに沿って東海~関東方面へ。
ついでに三陸沖に目を向けると、暖湿気を上空まで吸い上げる台風13号の様子がわかります。
この暖湿気が今夜から北海道方面に流れ込むので・・・北海道道東で大雨警戒ということになります。
まあ・・・・今日はこのくらいにしておきます。
いずれにせよ、今日いっぱい警戒モードを続けたらその後は晴れが続くということですね。
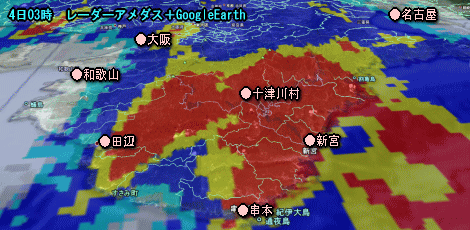
最後にオマケ・・・4日03時のレーダーアメダス合成画像。
災害が発生した地域が赤の32mm/h以上・・・表示上限のエリアに対応していることがわかります。
| 12時25分追記 昼飯を食いながら考えていたのですが・・・・・ここ一週間の台風12号がらみの計算値・・・いつも流線と降水を表示しているMSMというシミュレーションが、終始台風の速度を早めに計算していたように思います。 このため実況を見ながら遅め遅めに修正をかける必要が生じていたわけですが、それと同時に紀伊半島方面の降水量予測を上方修正しなくてはならない状況に。 まだ感覚的なところですが・・・・今後の台風へどう生かしていくべきか?考えどころだと思います。  これは、午前中愛知県から岐阜県にかけて南北にシャープな強雨帯が発生したときのレーダー画像(立体化したもの)。 昨日、この様子がMSMというシミュレーションで計算されましたが、一時的な計算結果として後に消えていました。 しかし、実際は一時的に計算された現象がこのように発現・・・これが持続したら岐阜県も大変な大雨になったことでしょう。 そして、12時のレーダー・・・  台風13号に流れ込む暖湿気による強い降水帯が関東の東海上に観測されていますが、この降水帯がもう少し西だったら・・・・紀伊半島まではいかなくとも、関東も恐ろしい大雨になっていたかもしれません。 遅い台風の恐ろしさを見せつけた台風12号・・・・ |
| 20時20分追記 明日(6日)北海道で大雨に警戒・・・ということが天気予報で呼びかけられているので、一応MSMの計算値だけは追記しておくことにしました。 暖湿気が流れ込む様子などは、朝掲載の解説等を読んでいただければわかると思います。  |
ご意見・ご質問等は、コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。
可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)
(当ブログはリンクフリーです)
2011年09月04日
台風12号・13号?の動向、大雨の今後(9月4日)
| 17時00分追記あり |
台風が遠ざかっても大雨がおさまりません。
テレビの天気予報では、台風の進路予想図が主役になっていますが、進路予想図から暴風域が消えたり、日本海に抜けたあとは急激に防災意識が低下してしまうものです。
しかし、今回の台風は、上陸前から大雨被害をもたらしたように、遠ざかっても大雨の尾を引きます。
このあたり、天気予報や報道番組でどう伝えていくのか?が難しいところでしょう。
さて、台風12号とは別に、気象庁発表の今夜の予想天気図には台風13号?が表示されています。
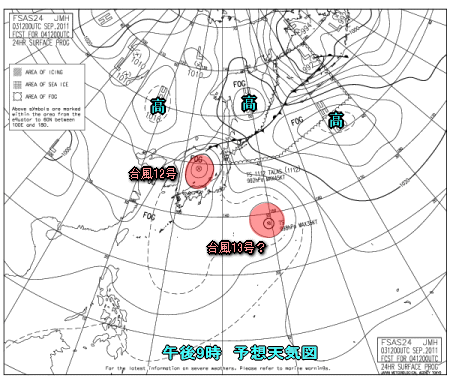
台風13号の動向も含めて、今日は①台風12号の動向と大雨の様子、②台風13号?の動向についてまとめておきました。
1、台風12号の動向
予想進路図が気になる方が多いと思いますが、ノロノロ台風の現在の位置や予想進路はコロコロ変化するものです。
ブログで表示するのは不適切なので、以下のURLを参考に最新のものを確認してください。
米軍台風進路予想(TC Warning Graphicをクリック。日本時間は+9時間)
http://www.usno.navy.mil/JTWC/
気象庁5日間予報
http://www.jma.go.jp/jp/typh/typh5.html
台風情報(文字情報:台風に関するニュースの元ネタ)
http://www.jma.go.jp/jp/typh/typh_text.html
地方気象情報(文字情報:「予想される雨量は○○ミリ」というニュースの元ネタ)
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/103_index.html
さて、詳細な雨や風の様子を気象庁のシミュレーションでチェックする前に、「木を見て森を見ない」ことにならないよう、気圧配置を上空の天気図と併せて概観しておきます。
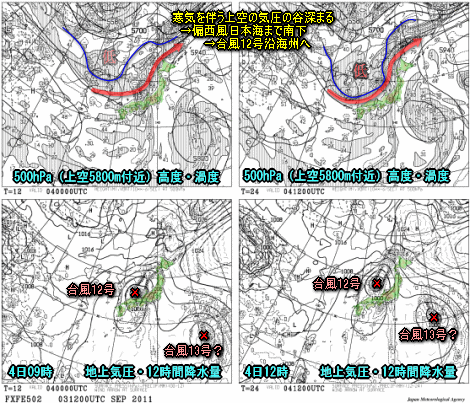
今回の台風がノロノロなのは、上空の偏西風が日本付近に南下していないからと説明されていますが、偏西風を南下させるのが上空の気圧の谷。
今朝の段階ではまだまだ浅いですが今夜にかけてやや深まって、偏西風(赤矢印)も南下してきます。
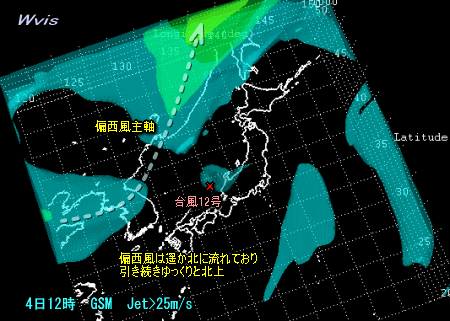
台風まではまだまだ遠いですけれど・・・・
また、この上空の気圧の谷、比較的強い寒気を伴っていて、気圧の谷が深まるとともに寒気も南下。
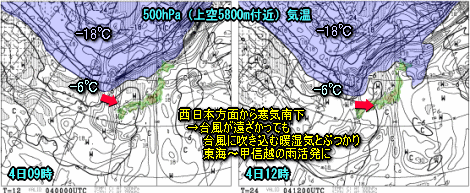
台風の反時計回りの風・・・台風の西側の北西風が寒気を引きづり下ろすというイメージでしょうか。
西日本方面から寒気が南下してきます。
寒気が南下すると、台風の東側から流れ込んでいた大雨の原料・・・暖湿気とぶつかることになります。
大雨が尾を引く原因がこれ。
暖湿気と寒気(冷涼乾燥空気)がぶつかる様子・・・・・・
まずは立体的に見ると・・・地上付近に暖湿気が流れ込み、上空から寒気が南下してきます。
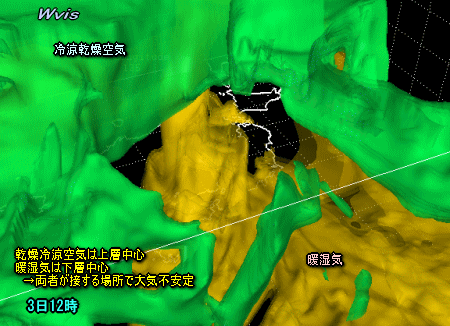
ちょっとわかりにくかったかな?・・・これを念頭において、二種類の異なる性質の空気が、台風を中心に回転するようにぶつかり合う様子をアニメで・・・・
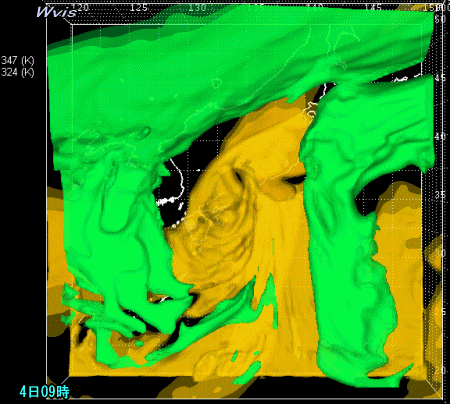
明日になると、台風の東に巻き込まれるように流れ込んでいた暖湿気(黄色)が、日本海北部まで進んだ台風に向かって南から一気に駆けあがるような流れに変化。
他方、西日本方面から寒気(冷涼乾燥空気:緑)が南下してきますが・・・このアニメではちょっとわかりにくいですが、東海付近に両空気のぶつかるラインできて・・・大雨をもたらす南北の降水帯が形成されそうです。
以上を踏まえて、具体的な雨と空気の流れの様子・・・MSMというシミュレーションで明日朝まで・・・・
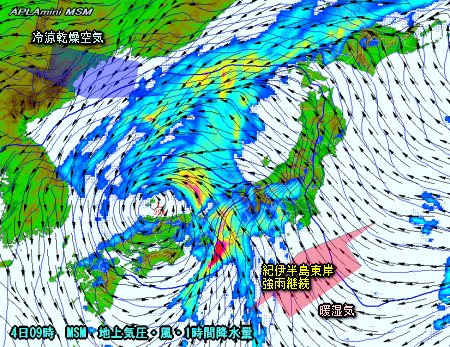
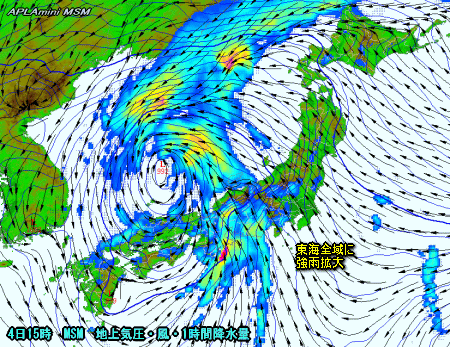
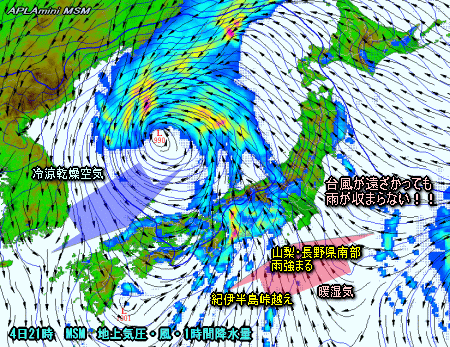
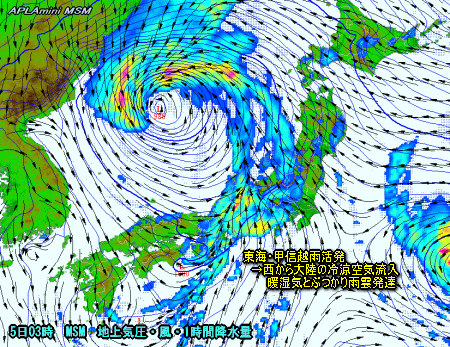
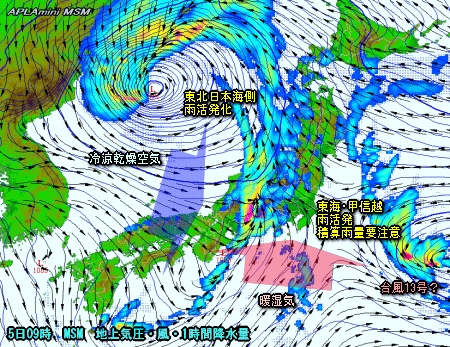
二つの空気のせめぎ合いの様子がわかるように、青と赤の矢印も書きこんでおきました。
台風が遠ざかっても、大雨のエリアがシャープになって東海・甲信越方面で継続することが読みとれると思います。
暴風域が無くなっても、南下してくる寒気の影響で温帯低気圧の性質に変化してきているだけなので、かえって風速15m/s以上の強風域が拡大する傾向。
風速に関しては地形的な影響が大きいので、台風進路予想図の強風域や府県天気予報の風の予報を参考にしつつ、この図の風向きから、どのような風が吹くのか?イメージしてみてください。
各地の府県天気予報: http://www.imocwx.com/yohoud.htm
なお、Kasayanの住んでいる長野で大雨が計算されている明日朝の様子については・・・・拡大して・・・・
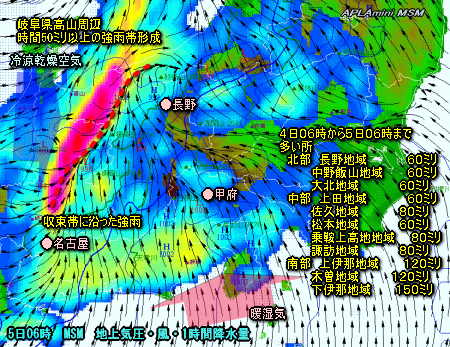
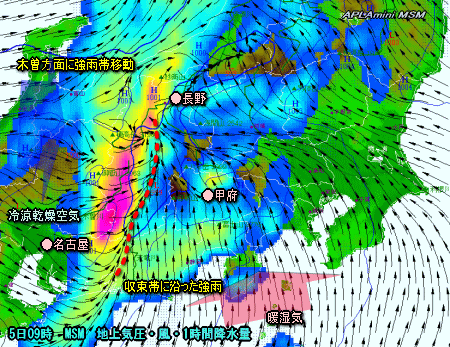
図に掲載しておいた予想降水量は、長野地方気象台が今朝発表したもの。
明日朝6時までの予想降水量ですから、そこから先の時間帯が問題・・・今日の夕方に発表される大雨情報はチェックしたいところです。
一番上に掲載しておいた地方気象情報のリンクで最寄りの地域の気象情報を読むことができますので、ご参考までに。
2、台風13号?の動向
気象庁発表の今夜の予想天気図にはTSと表示されていますから、気象庁は風速17.2m/s以上・・・台風まで発達すると予想しているわけですが、台風になれば順番からして13号。
台風12号のチェックと同様・・・「木を見て森を見ない」のは、シミュレーションによって天気チェックするときに陥り易い過ちなので・・・上空の気圧配置も含めてチェック・・・・・
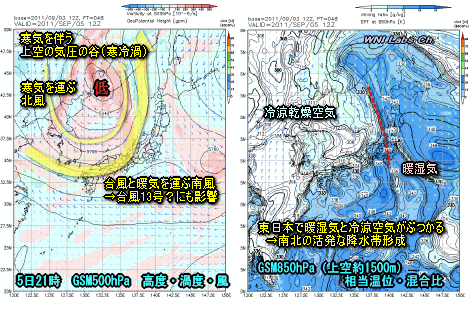
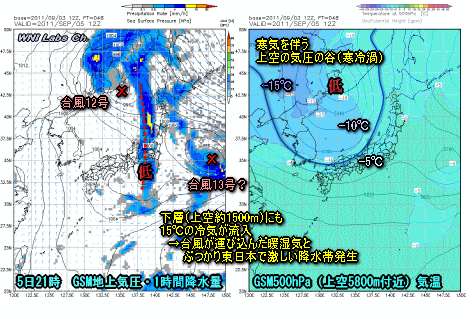
先に見た上空の気圧の谷が一気に深まって偏西風も日本上空まで南下。
計算どおり偏西風に乗れば北東に進み始めますから、なんとか関東沖接近までで済みそう・・・という計算結果が出ていますが・・・台風12号のようなデッカイものが存在しているとシミュレーションが多少暴走することがあるので・・・・しばらく疑いの目でチェックを続けておきたいところです。
| 17時00分追記 紀伊半島方面の大雨は今日中に峠を越えそうな気配。 東海~関東の雨については、これからが注意を要する状態であることは、今朝の記事でご理解いただけたと思いますが、その量的な計算値については、今日日中、新たな計算値が発表されるたびにコロコロ変化している状態です。 この場合、「何を信じればよいのか?」という判断をするのではなく、「安全マージンをとる必要がある」という判断が適切です。 というのも、降水が少なくてすむという積極的なデータはなく、ゲリラ雷雨が発生してもおかしくないと考えられる状況以上の暖湿気(雨の原料)は明日も流れ続けるからです。   最新の短期予報解説資料というプロ用の資料からの抜粋ですが、明日の大雨の着目点は東海沖に発生するシアーライン。 前線と似て空気の流れが急変する場所とイメージすれば良いと思いますが、雷雲が発達しやすいシアーラインが東海沖を東進。 東海沿岸部を中心に活発な雨が予想されるというのが気象庁の見解です。 各地の気象台が発表する予想降水量は、以下の地方気象情報でチェックできます(ニュースや天気予報の「○○地方は多いところで◎◎ミリ」と言っている元ネタ)。 地方気象情報: http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/105_index.html 最新のMSMデータにシアーライン等の書き込みをしておきましたので、以下に掲載しておきます。   (気象庁発表の予報の最終製品といえる)府県天気予報を読みながら、具体的な雨の降り方をイメージするために使ってください。 (用語の定義にしたがって読まなければ無意味です) 府県天気予報: http://www.imocwx.com/yohoud.htm 用語の定義: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/mokuji.html |
ご意見・ご質問等は、コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。
可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)
(当ブログはリンクフリーです)
2011年09月03日
台風12号の進路と風雨の変化(9月3日)
| 10時00分 17時50分 追記 |
台風上陸間際のニュース番組では、気象会社からの中継で昔の同僚の老けた顔を見ることができて・・・いつも懐かしい気持ちになります。
昨日は「絶対俺はテレビなんかにゃ出ない」と言っていたヤツが、したり顔で解説をしているのを見て思わず笑ってしまいました。
さて、西日本各地の防災担当者の方々は眠れぬ夜を過ごされたと思いますが、日が昇っても上陸しない台風に「バカ野郎!!!どうなってるんだよ!」とイライラされていると思います。
最新のシミュレーションデータをご紹介する前に、まずはノロノロ台風と台風を押し流す偏西風の関係を、新しい情報でチェックしておきましょう。
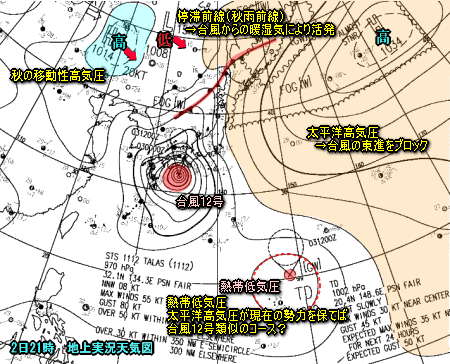
昨夜21時の地上実況天気図・・・お馴染みの天気図ですね。
台風が日本の東にある太平洋高気圧にブロックされて東へ進めないということは一目瞭然。
そして、北へノロノロという点について、太平洋高気圧の西縁の弱い南風に流されているから・・・ということになります。
(南の新しい熱帯低気圧・・・計算もイマイチ・・・なんで、今日は見なかったことにしちゃいます)
次は同時刻の上空5900m付近の天気図。
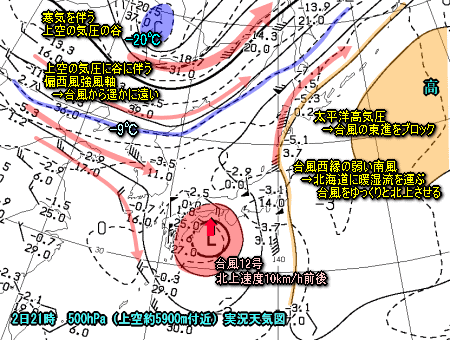
大陸には等圧線(正確には等高度線といいますが同じに考えてOK)が凹になった部分・・・上空の気圧の谷があります。
上空の気圧の谷直下にあるのが偏西風ですが、台風からずいぶん離れています。
これに乗ったら急速に北東進するのですが、この距離を見る限りそうならないことは容易に想像できるでしょう。
もう一点、大陸沿岸まで-9℃の寒気が南下していて(青のライン)、ここから北側が秋の空気。
台風が偏西風の南側の弱い南西風に乗って北東進するに従って、この寒気が台風に巻き込まれて、(暖湿気で発達する)台風が(暖気と寒気が混ざり合う力で発達する)温帯低気圧化することが予想されます。
ゆっくりと北東進して、温帯低気圧化するという説明ができます。
(温帯低気圧化といっても、性質が変化するだけで風や雨が弱まるわけではありません)
雲の様子も含めてイメージすると・・・・
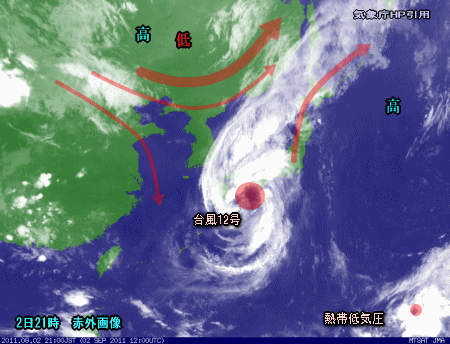
以上を踏まえて、立体的に偏西風と台風の位置関係を確認しておくことにします。
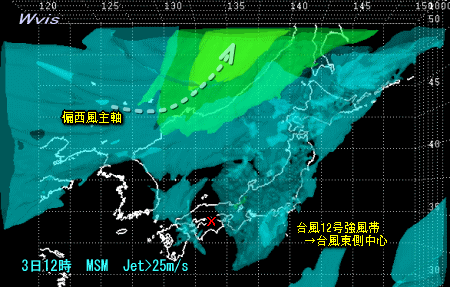
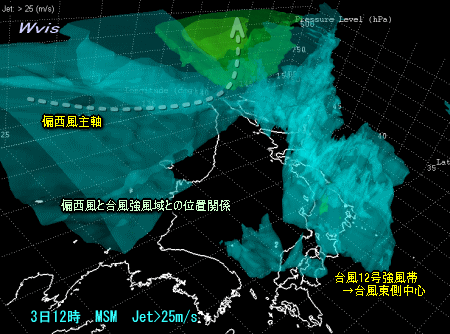
今日(3日)12時の予想ですが、あだまだ偏西風までの距離は大・・・ノロノロは続きそうですね。
現在の台風の様子・・・これが未来の空模様を考えるときの基本になりますからとても大切なんですけど・・・・十分すぎるほどご理解いただけたのではないかと・・・・・
米軍台風進路予想(TC Warning Graphicをクリック。日本時間は+9時間)
http://www.usno.navy.mil/JTWC/
気象庁5日間予報
http://www.jma.go.jp/jp/typh/typh5.html
台風情報(文字情報:台風に関するニュースの元ネタ)
http://www.jma.go.jp/jp/typh/typh_text.html
(詳しい実況把握の方法については、昨日の記事をご覧ください)
さて、最新(初期値03時)のMSMという気象庁のシミュレーションで、風の様子(矢印)と雨の変化をチェックします。
特に雨が強そうな場所など、図から読みとれそうなことを簡単に書き込みしておきました。
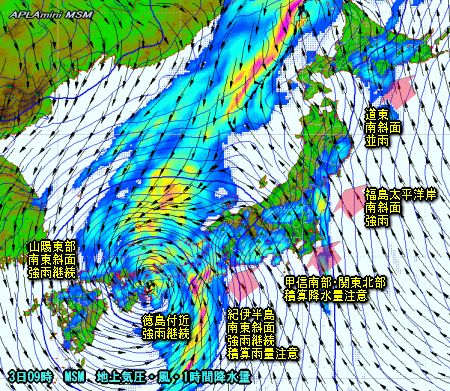
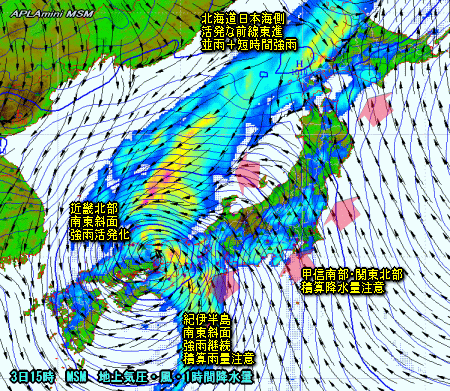
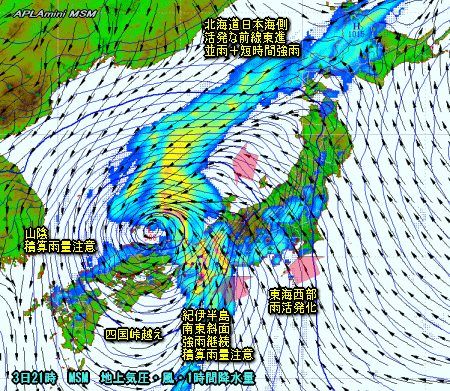
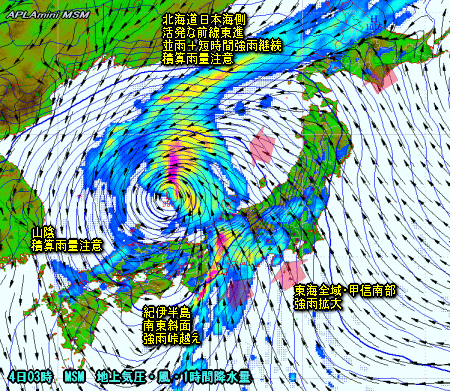
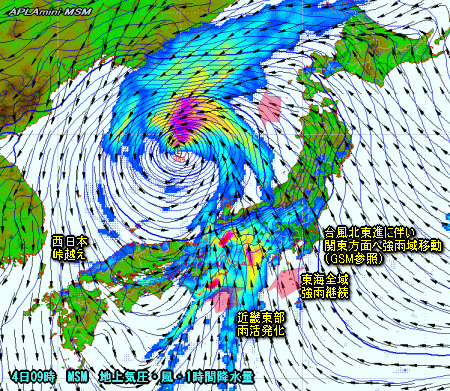
今夜、台風が日本海に抜けても、台風に流れ込む暖湿気は南岸から吹き込み続けますから、暖湿気が強風に流されてぶつかる山の斜面などを中心に、まだまだ雨が続きます。
強雨のエリアが非常にゆっくりと東進するので、並雨が降っていたところで急に雨が強まって、積算の降水量が増加して洪水や土砂・・・・・ここはテレビの天気予報で耳にタコですね。
このブログでは、湿った暖かい空気(大雨の原料)の流れ込みが、どのように変化するのか?ということをご紹介しておきます。
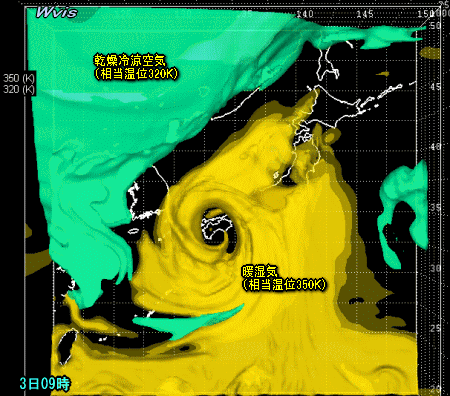
上でご紹介したものとは少々異なるGSMというシミュレーションで、暖湿気(相当温位)の様子をアニメにしました。
暖湿気とは正反対の冷涼乾燥空気も併せて表示させておきましたが、これが暖湿流とぶつかることによって起こる北海道付近の前線の活発化の原因を紹介したかったから。
平面のアニメ(MSM)で見るとこんな感じ。
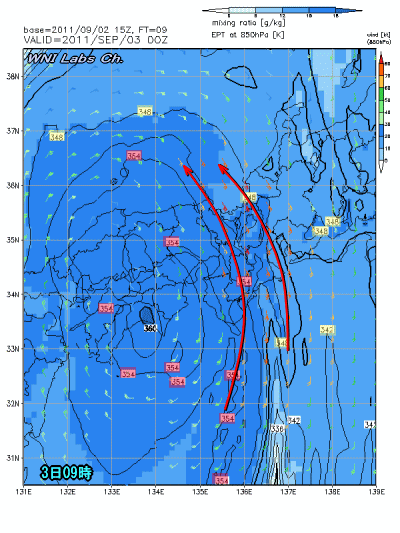
数字を赤く塗った部分が上で見た黄色のエリアに相当します。
そして、水色の濃い部分が湿り気の多いエリア(混合比)で、風の強いところに矢印を引いておきました。
流れ込む暖湿気が特に強風によって山にたたきつけられる部分で雨が活発化するようですね(雨のシミュレーションと対比させてみてください)。
また、明日になると南岸に南北の強い強雨帯が形成されますが、太平洋高気圧の乾燥した下降流が南岸に割り込んでくるので、性質の異なる空気が激しくぶつかる場所・・・前線帯が形成されるようです。
さて、次は気になる風の様子・・・Kasayanの住む長野県では梨や桃、ずいぶん膨らんだリンゴの実がどうなるのか?という点がとても気になるところです。
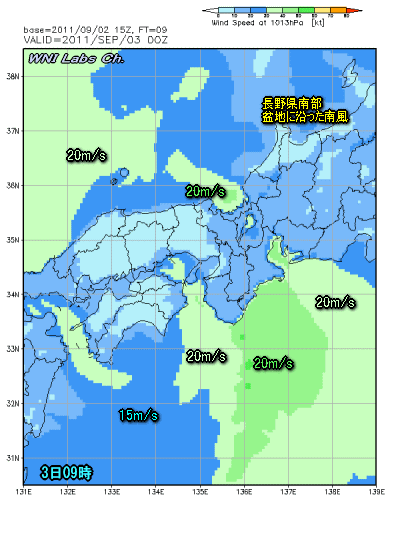
地上付近の風速ですが、このアニメを見て、思いのほか風が弱いじゃん・・・と思われるかもしれませんが、今朝7時のアメダスをチェックしてみると・・・・
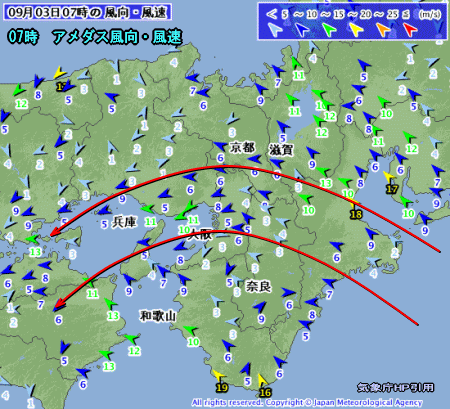
計算値とほぼ一致しているようですね。
もっとも、これは平均風速ですから、瞬間風速では1.5~2倍の風速は想定しなくてはなりません。
そのあたりを考えて、上でご紹介した風向のシミュレーションと併せて検討してみてください。
ちなみに、Kasayanが住んでいる長野県付近では・・・・・台風の雨が活発化する明日朝・・・・
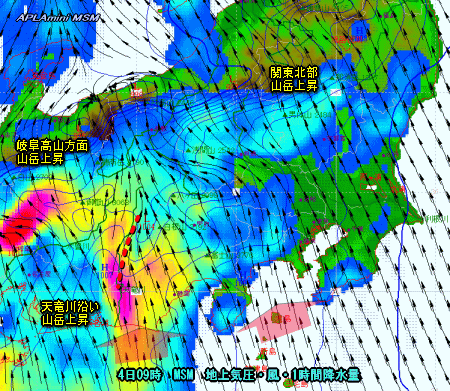
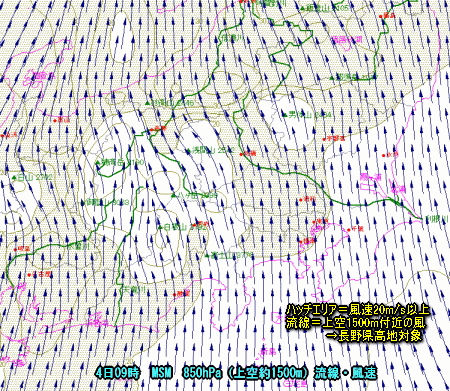
下の図は地上付近から上空1500m付近(高原や山など)・・・・南風で沿岸中心に20m/s以上。
地上付近の風速が弱めでも、少しだけ上空では強い風が予想されています。
悪夢のようなリンゴ台風をイメージする必要はないかもしれませんが・・・ちなみに長野地方気象台が発表している明日の風の予報(3日05時発表)は長野県中北部で「南の風 やや強く」・・・つまり「10m/s以上15m/s未満 風に向かって歩きにくくなる。傘がさせない。」ということになります。
各地の府県天気予報: http://www.imocwx.com/yohoud.htm
今朝はこのくらいにしておきましょう・・・・今日は家にいるので・・・・何か気付いたことがあれば、追記あるいはTwitterでつぶやきたいと思います。
| 10時00分追記 「詳しすぎてわからない」・・という”つぶやき””があったので・・・・追記! このブログ・・・テレビやネットの天気予報を見て、「暖かく湿った空気が流れ込むので・・」という解説に「じゃあこれから暖かく湿った空気はどうなるのよ?」とか、「台風を押し流す上空の風が近くを流れていないんですね」という解説を聞いて「上空の風ってどこにあるのよ?これから流れに乗らないのかよ?」なんて疑問を持ったときに役立つように作ったつもりです。 それに「○○地方で400ミリ」なんて放送されていますけど、○○地方全域でベッタリ降り続けているわけじゃありません・・・もっと詳しく知ってみたいと思いませんか? わかるところだけ・・・疑問を解決するために・・・・読んでいただければ効果があるかと思います。 わからないところがあってもイイんです・・・飛ばし読みすれば・・・・。全部完璧にわかってしまうようなら、気象予報士なんて必要なくなっちゃいますから。 |
| 17時50分追記 台風12号・・・今朝掲載したシミュレーション(MSM)より約6時間遅れで推移しているようです。 雨や風の計算値はそのままで良いとして、位置を修正してイメージを再構築してください。 さて・・・雨が長く降り続いて・・・洪水・土砂災害がニュースなどで注意喚起されていますが、同じ場所で雨が降り続くというコトがあまりイメージしにくかったりしませんか? このところズバリのシミュレーション計算値ばかり掲載していて、基本的な天気図をチェックしてないんじゃない?と思われてもアレなんで、12時間降水量がイメージしやすいプリント用の天気図に書き込みをしてみました。    青く塗ったところ・・・点線の内側ほど連続した雨のイメージになる場所。 (0ミリの一本内側を塗るのがコツです・・・気象予報士受験予定の方・・・) +161などと数字がスタンプされている場所が12時間降水量の極値にあたる場所。 明日朝までは岡山県付近、明日夜にかけては岡山県と静岡県付近にスタンプされています。 気象レーダーでチェックしたり、アメダスの降水量をチェックする際の参考にしてみてください。 ところで・・・・台風12号じゃなくて・・・台風13号、明日朝までに発生することが予想されています。  その後の進路は・・・上空の気圧の谷が深まって偏西風も南下・・・・関東に接近する前に北東方向へ・・・という計算がされていますが、台風12号チェックの際に横目で確認しておきたいところです。 |
ご意見・ご質問等は、コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。
可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)
(当ブログはリンクフリーです)
2011年09月02日
台風12号の動向と雨や風の実況把握方法(9月2日)
| 本日は早朝から外出するので(台風対策・・・)、朝は簡易な記事とし、昼前後と夜に更新あるいは追記いたします。 12時30分追記あり、18時45分追記あり |
いよいよ週末の台風上陸・・・・役所の防災担当者の方をはじめ、この週末を24時間体制で台風対策することを余議なくされた方々の御心中察します。
今日もテレビやネットの天気予報にプラスアルファになる?話を中心に・・・・
米軍台風進路予想(TC Warning Graphicをクリック。日本時間は+9時間)
http://www.usno.navy.mil/JTWC/
気象庁5日間予報
http://www.jma.go.jp/jp/typh/typh5.html
台風情報(文字情報:台風に関するニュースの元ネタ)
http://www.jma.go.jp/jp/typh/typh_text.html
さて、今回の台風、台風が大型で影響範囲が大きいため、高潮や地形的に強風が吹きやすいなど風向に関する被害を考える場合以外に、ピンポイントで上陸地点を考えても生産的ではありません。
むしろ、気象庁発表の台風情報(文字情報や進路図等)を適時参考にし、「何が起こるのか?」「いつ起こるのか?」「いつまで続くのか?」「どうして起こるのか?」などと考えつつ実況把握に努め、目先直後に起こりうることを想定したほうが防災上非常に重要だと思います。
そこで、まずは実況把握について、Kasayanがオススメする一つの方法をサンプルを使ってまとめておきたいと思います。
気象庁HP: http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
以下の図は、昨日17時頃、山口県方面で一時間に50ミリを超える雷雨となった時の様子。
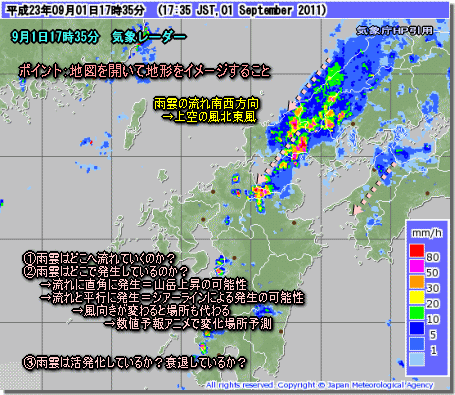
まず、多くの方が雨の降り方をチェックする際に使用すると思われる気象レーダー。
ザッと考えられるチェック方法①~③を書きこんでおきました。
直近の画像をチェックするだけでなく動画表示をして、雨雲の発達・衰弱や移動の様子を把握するのは当然ですが、今回の大雨は台風に流れ込む大量の暖湿気によってもたらされますから、「どこで暖湿気が上昇して雨雲を発達させるのか?」に着目することが必要です。
重要なのは、まず「地図を開いて地形を把握」すること。
天気予報では、「暖湿気が山にぶつかって・・・」と説明されますが、上昇気流が発生するのは山にぶつかる場合だけではありません(昨日の関東の大雨は昨日の記事参照)。
山を迂回した風が、山の風下で合流(収束)する場所でもライン状に雨雲が発生し、大雨をもたらします(シアーラインによる雨)。
昨日の山口県方面の大雨がそれ。

風の収束は基本的にアメダス風向観測値を用いて考えることになります。
地上の地形が影響するため判断が難しいと思いますが、細かな観測値にこだわらず、地形を意識しながら大ざっぱに考えるのがコツです。
また、レーダーのように観測時間をさかのぼって、風向変化も把握するようにしてください。
ちなみに、昨日のレーダー画像に、MSMという計算値の風の流れ(流線)を重ね合わせて見たものが以下の図ですが・・・・
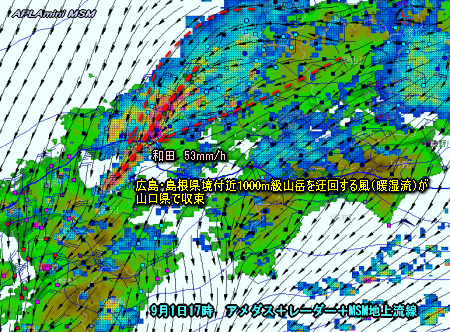
島根県・広島県の県境にある1000m級の山を迂回した風が山口県付近で合流して帯状の強雨帯が形成されており、計算値の流線から降水帯を予測したり、アメダスを使って目先の大雨を予測することが有効であることを物語っています。
このような現象は、上記地域に限らず、今日は前線に吹き込む暖湿流で雨が活発になっている北海道や被災地も含めて、全国的に発生する可能性が考えられます。
台風の北上に伴って風向が少しづつ変化して、大雨の位置も微妙に変化しますから、台風の動きも意識しつつ、南東斜面を中心に実況把握をするのはもちろん、風の収束についても着目してチェックしてみてください。
なお、南東斜面に警戒を要するのは、基本的に台風の東側。
昨日の山口県のように、台風の西側では北寄りの風が吹き、強い暖湿流が流れ込んでくるおそれもありますから注意してください。
時間もありませんから、いつものMSMという気象庁の計算値を掲載しておきます。
非常にリアルに見えるので、「自分の頭上は大丈夫か?」という目で見てしまいがちですが、あくまで傾向を表示しているものと考えて、実況把握をする際の参考資料にしてください。
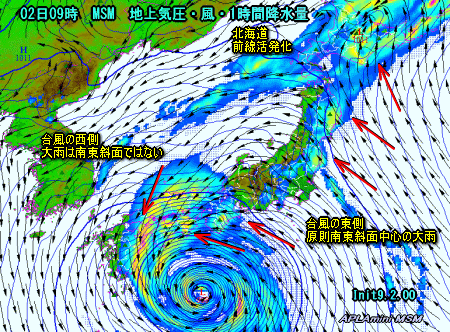
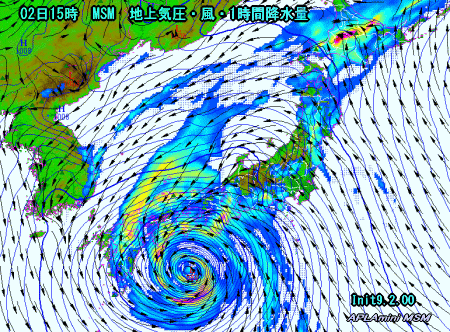
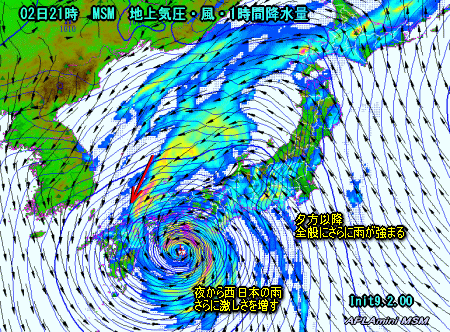
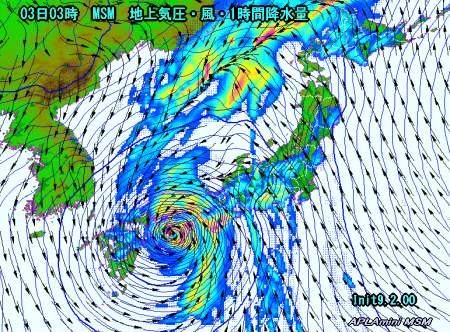
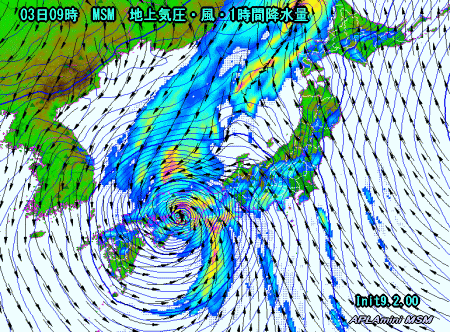
中間を補完するデータ(同じMSMモデル)WeatherReport
http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/chushikoku.html
【2日21時拡大】
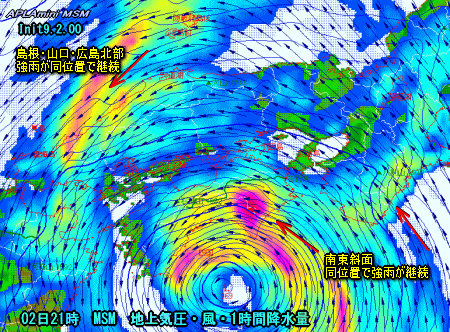
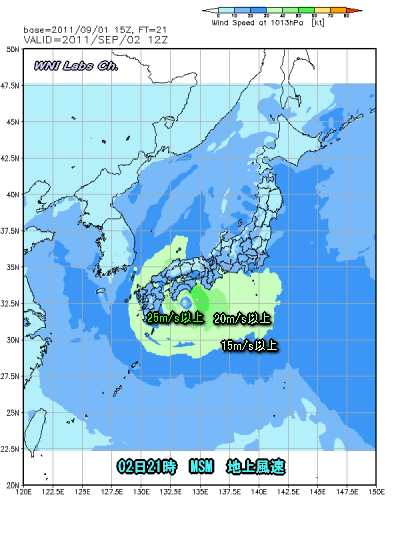
| 12時30分追記 今朝の記事は実況把握の方法を中心に書きましたが、テクニックばかりで大雨を裏付ける現象をイメージする情報に欠けていました。 そのため、暖湿流のイメージがイマイチ沸かなかった方もおられたかも? テレビの天気予報でも、「台風の回りを反時計回りに回って流れ込んだ暖かく湿った風のせいで・・・」という解説とともに赤の矢印が表示されたりすると思いますが・・・・。  黄色の部分が相当温位350Kというとても湿った暖かい空気を表しています。 台風の目の周辺に上昇気流の強い場所があるので、まるで竜巻のように上空に暖湿気が吸い上げられている様子が計算され、その東側から日本に暖湿気が流れ込んでいます。 そして、緑の部分・・・乾燥して冷たい空気。 北海道付近で前線のまとまった雨が降っていますが、暖かい空気と冷たい空気がぶつかっているから・・・ 本当は黄色と緑の部分が接しているんですけど、わかり易いように両極端の性質の空気を表示させて間を開けて表示しました。 日本全国どこでも上昇気流さえ発生すれば大雨になるというのが理解していただけました? 次はノロノロの理由・・・テレビの天気予報で伝えられてました?  今夜21時の台風と台風を押し流すジェット気流の位置関係。 緑色のジェットの主軸は大陸沿岸にありますけど、その南縁はそこそこ日本海沿岸に近いんですよね・・・・ 流れがU字になっている部分・・・上空の気圧の谷が計算以上に深まれば、台風が多少早めに北東進したり、上陸直前にフラフラと東へ流れたりということがあるかもしれません。 最後は、今朝の記事の補足。 レーダーを見ていると、アメダスで確認した地上付近の風と雲の流れる方向が異なることに気付かれた方もおられるのでは? 暖湿気が山にぶつかったり収束したりして雨雲が発達するわけですが、発達した雲は上へモクモク・・・地上付近の風向と上空の風向は異なりますから、 発達した雨雲は上空約3000m付近の風に流されやすい傾向にあります。 上空の流れをチェックするには・・・・  ウインドプロファイラというスゴイ武器が気象庁にありますから、アメダスと併用してこれもチェックしてみてください。 ウィンドプロファイラ: http://www.jma.go.jp/jp/windpro/ |
| 18時45分追記 夕方のニュースを横目で見ていましたが、「台風の東側に湿った空気が・・・南東斜面で雨雲が活発になって・・・」ばかり。 予想される降水量も気象庁発表をそのまま伝えるだけなので、なんで気象予報士が解説しなくちゃならないの?・・・いくら台風の予想は大本営・・・気象庁発表しか許されていないとしても、そろそろ全局横並びの内容からは脱却してもらいたいと思います(自分が担当していないから言えるんですけどね・・・) 最新のシミュレーションデータ(15時初期値MSM)を明日の午後までまとめておきました。     また、実況把握の参考になる資料・・・さらに掲載しておきました(自分が把握するために作ったものの流用だったりして)。 上空の風のほうが雨雲発達と対応が良くなっているのが山梨県方面。 観測地点は少ないですけど、アメダスでらちが明かない場合はウィンドプロファイラも多用してみてください。    |
ご意見・ご質問等は、コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。
可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)
(当ブログはリンクフリーです)
2011年09月01日
台風12号の動向と雨・風の変化(9月1日)
天気予報にとどまらず、ニュースでも台風がトップ項目に挙げられるようになってきましたから、具体的な予想降水量とかいつ頃から暴風になるのか?という話は頻繁に目にするようになると思います。
わざわざブログで同じことをまとめも意味がないので、天気予報やニュースを見た後で読んでいただくとプラスアルファになるようなことに絞って書いていきたいと思います。
とはいっても、このブログをご覧になる方が一番気にしていることはノロノロ台風の予想進路だと思います。

上空9600m付近・・・かなり高いところの天気図ですが、台風の北側に高気圧があって北上をブロックしていることがわかります。
ボチボチこの状態が解消して北上を開始することになりそうですが・・・・

テレビではこればっかりの・・・気象庁1日午前3時発表の進路予想図ですが、何度もご紹介してきた各国のシミュレーションモデルもほぼ同様のコースに収斂してきました。
速度に関しては数時間のバラツキがありますが、スーパーコンピューターのはじき出す結果はほぼこれで代表して考えることができそうです。
米軍台風進路予想(TC Warning Graphicをクリック。日本時間は+9時間)
http://www.usno.navy.mil/JTWC/
気象庁5日間予報
http://www.jma.go.jp/jp/typh/typh5.html
また、多少計算値がズレるようなことがあっても、台風が大型である以上、受ける影響に大差はありませんから、上陸地点がどこか?ということにこだわるのはあまり生産的ではありません(高潮を除く)。
ということで、ここからは何が起こるのか?という点について、天気予報では詳しく伝えてくれない点を中心に考えていきたいと思います。

いきなりですが、今朝6時の関東の雨の様子を立体的に加工したもの。
関東平野西部山岳地帯に偏って強い雨が降っていますが、これは台風から流れ込む湿った暖かいムシムシ空気(雨の原料)が南東風に乗って山の斜面にぶつかっているから。
なんで、こんな図をご紹介したかといえば、山の風上斜面で特にまとまった雨が降る・・・という傾向が、台風一過まで続きそう・・・ということをお伝えしたかったからです。
これを平面で見るとこんな感じ・・・・

ご覧いただければわかると思いますが・・・・台風が南にあるとつい忘れがちなのが北海道方面ですけど、北海道の西には寒気が流れ込んできていますから、湿った暖かい空気と寒気がぶつかって前線ができて・・・雨が活発になっています。
暖かく湿った空気(暖湿流)だけを見てみると・・・・

台風からの暖湿流が関東から西日本へと拡大傾向・・・・西日本の山の南東斜面には要注意ということですね。
もちろん、台風本体が接近してくると並雨も降るようになりますから、南東斜面の雨は通常の雨に加算されるように降るということ。
ノロノロ台風ですから長時間の並雨もありますから、全体の降水量が増えて・・・ありきたりですけど土砂災害や洪水に警戒ということになります。
具体的にどんな雨が降るのか?ということですが・・・・まずは今日の雨の様子から。

いつもと違って、暖湿流の様子が顕著に現れる上空1500m付近の風の流れを表示させています。
暖湿流が強まって、風がぶつかる南東斜面の雨が強まる・・・ということを読みとっていただければOKです。
次は台風が上陸しそうな3日の朝から夜にかけての様子を気象庁GSMモデルでチェック。


進路予想図の暴風域も対応させてチェックしていただくのがよいと思います。
丸一日かけても、近畿地方を抜けるだけですから、影響がどれだけ続くのか・・・想像できると思います。
また、台風上陸が紀伊半島だとか、四国だといっても影響が大きく変わるものではない・・・ということもわかりますよね?
(風向きは大きく変わりますから、港湾関係の方など高潮に警戒される方は風下にあたるのか?アメダス等で風向変化をコマメにチェックすることをおすすめします)
| 13時30分追記 紀伊半島で雨活発化。暖湿流の様子はウィンドプロファイラ1km参照。沿岸部台風中心への風。     |
| 17時20分追記 進路予想をご覧になっている方・・最新の情報が発表されるにしたがって上陸地点が微妙に西に変化していることに気付いておられると思います。  MSMというGSMより解像度の高いシミュレーションの遠投距離?が台風の接近時間まで届きました。 進路予想図や先にご紹介したGSMより西にズレていますが、この程度のブレは台風を押し流す上空の強い流れがない場合にはありうることです。 また、陸地に接近するタイミングで東寄りに進む場合もありますから、完全に予報円だけの安全マージンを考えるべきとは言いませんが、最低でも潮岬~高知市の間程度の安全マージンは採っておく必要があると思います。 (上陸寸前で東寄りに進み、当初の上陸地点近くまで戻る場合があるのは、北東に向かう上空の強い流れに接近するので計算値以上にその影響を受けたり、陸地(山岳)の影響があるからです。) コースがズレた際、これまでの計算をご覧いただいたように、雨の降り方や風速については大きく変化はありませんが、風向に大きな変化が生じる場所があるはずです。 その場所が風下にあたる海岸であれば、満潮時を中心に高潮の恐れが生じます。 ピンポイントで上陸地点を予測したいという気持ちになりがちですが、(二位じゃダメなんですか?という)スーパーコンピュータの限度と、人間によるアナログな修正の限界を越えたところの話ですから、あくまで実況重視(アメダスとレーダーを駆使)、安全マージンを考えた判断と対策・・・これが必要だと思います。 実況重視の方法については明日の記事で・・・・ |
最後は、専門天気図・・・・Kasayanがいつも寝ぼけ眼でシコシコとチェックしている図に、多少解説めいたことを書きこんで掲載しておきますので興味のある方だけどうぞ・・・・。
台風がノロノロの原因、暖湿流の方向が変化していく様子、などをわかる範囲で参考にしていただければ掲載した意味があるかな?・・・と思います。


ここまで読んでいただいて・・・・お気づきの方もいらっしゃると思いますが・・・・いつもKasayanは予報をしていないんですよね。
誰でも手に入れられる資料から何が読みとれるのか?をまとめているだけ。
でも、資料の解説を読んでいただいて、予報を読んでいるような気持ちになっていただけたら・・・・それは読んだ方が無意識に頭の中で予報を組み立てているということです。
実はそれがKasayanの意図しているところ。
今日11時から、明後日3日の気象庁の通常の予報(短期予報)が発表されるようになります。
このブログでイメージされた空模様を思い浮かべながら気象庁の予報を読んでいただくと、今までとは違う深読みができると思います・・・そして、友人に解説したら・・・あなたはお天気キャスターです。
是非試してみてください。
府県天気予報(予報文):http://www.imocwx.com/yohoud.htm
今日、風や波についてあまりコメントできませんでしたが、時間があればTwitterでつぶやくか、追記をしたいと思います・・・時間があれば・・・・ですけれど。
ご意見・ご質問等は、コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。
可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)
(当ブログはリンクフリーです)


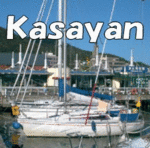


 はてなに追加
はてなに追加 MyYahoo!に追加
MyYahoo!に追加 del.icio.usに追加
del.icio.usに追加 livedoorClipに追加
livedoorClipに追加





