2009年11月05日
天気予報のチェック方法(1)
インターネット上に溢れる気象情報・・・・
どの情報を、いつ、どのように見ればよいのか・・・・知ってますか?
間違った使い方してませんか?
天気予報のチェックフロー兼リンク集を用意しました。
1、天気予報チェックの初歩の初歩
①予報をコマメにチェックする
基本中の基本なんですけど、予報は一日3回気象庁から発表されます。
Yahoo天気だろうと、ウェザーニューズの独自天気予報であろうと、ベースは気象庁の予報(計算値)ですから、予報の根本が変更されるのは更新時間が微妙に違っても、同じです。
新しい予報が出ても、古い予報を見て行動していたのでは意味ないですよね。
そこで、予報のハズレで痛い思いをしたくなかったら、午前5時5分、午前11時5分、午後5時5分の3回、気象庁発表の予報を確認してください。
※天気マークの天気予報 (今日、明日、明後日はページ内で選択してください)
(明後日の予報は、午前11時と午後5時にしか発表されませんのでご注意!)

②天気マークの「裏」を読む
次に、天気マークだけでは、マークに表示されない「一時雨」とか「夕方から晴れ」という予報の微妙な表現を知っておく必要があります。そこで予報文も読んで、予報の内容を正しく理解します。
※予報文

③「のち」って何時のこと?
また、「一時」とか「のち」の天気変化のタイミングまで気になる方は、いわゆるメッシュ予報を使えば、そのタイミングを知ることができます。
※メッシュ予報(分布予報)

メッシュ予報を見るときは、「オッ、雨のエリアがギリギリセーフだな」なんて見方はしないで、「およそそんな傾向だな」程度にしておいたほうが無難です。
メッシュのマス目が20キロもありますから(5キロのものもあります)、マス目一つや二つズレて予報がハズレることはいくらでもありますから。
また、天気が変化するタイミングも2~3時間は余裕をもってみておいてください。
ちなみに、メッシュ予報の格子点をピックアップして時系列の表にすれば、いわゆるピンポイント予報になります。ということは・・・コンピュータまかせのピンポイント予報がどれだけ怪しいかがわかりますよね。
④どうしてこんな予報になったの?
予報がはずれたらどうなるか?・・・・予報の理由を知りたい方は、気象庁が発表している公式?の天気概況を読んでみてください。
天気図が読めなくても、予報を出した人の説明を読めば、予報のアヤシサも見えてくるかもしれませんよ。
※天気概況(ページの下のほうにあります。ご自分のエリアを選択してからご覧下さい)

さらに裏技へと続きますが・・・・続きは次回の記事で・・・・
ご質問・御意見・ご要望がありましたらコメントお待ちしております。
どの情報を、いつ、どのように見ればよいのか・・・・知ってますか?
間違った使い方してませんか?
天気予報のチェックフロー兼リンク集を用意しました。
1、天気予報チェックの初歩の初歩
①予報をコマメにチェックする
基本中の基本なんですけど、予報は一日3回気象庁から発表されます。
Yahoo天気だろうと、ウェザーニューズの独自天気予報であろうと、ベースは気象庁の予報(計算値)ですから、予報の根本が変更されるのは更新時間が微妙に違っても、同じです。
新しい予報が出ても、古い予報を見て行動していたのでは意味ないですよね。
そこで、予報のハズレで痛い思いをしたくなかったら、午前5時5分、午前11時5分、午後5時5分の3回、気象庁発表の予報を確認してください。
※天気マークの天気予報 (今日、明日、明後日はページ内で選択してください)
(明後日の予報は、午前11時と午後5時にしか発表されませんのでご注意!)

②天気マークの「裏」を読む
次に、天気マークだけでは、マークに表示されない「一時雨」とか「夕方から晴れ」という予報の微妙な表現を知っておく必要があります。そこで予報文も読んで、予報の内容を正しく理解します。
※予報文

③「のち」って何時のこと?
また、「一時」とか「のち」の天気変化のタイミングまで気になる方は、いわゆるメッシュ予報を使えば、そのタイミングを知ることができます。
※メッシュ予報(分布予報)

メッシュ予報を見るときは、「オッ、雨のエリアがギリギリセーフだな」なんて見方はしないで、「およそそんな傾向だな」程度にしておいたほうが無難です。
メッシュのマス目が20キロもありますから(5キロのものもあります)、マス目一つや二つズレて予報がハズレることはいくらでもありますから。
また、天気が変化するタイミングも2~3時間は余裕をもってみておいてください。
ちなみに、メッシュ予報の格子点をピックアップして時系列の表にすれば、いわゆるピンポイント予報になります。ということは・・・コンピュータまかせのピンポイント予報がどれだけ怪しいかがわかりますよね。
④どうしてこんな予報になったの?
予報がはずれたらどうなるか?・・・・予報の理由を知りたい方は、気象庁が発表している公式?の天気概況を読んでみてください。
天気図が読めなくても、予報を出した人の説明を読めば、予報のアヤシサも見えてくるかもしれませんよ。
※天気概況(ページの下のほうにあります。ご自分のエリアを選択してからご覧下さい)

さらに裏技へと続きますが・・・・続きは次回の記事で・・・・
ご質問・御意見・ご要望がありましたらコメントお待ちしております。
2009年11月06日
天気予報のチェック方法(2)
インターネット上に溢れる気象情報・・・・
どの情報を、いつ、どのように見ればよいのか・・・・知ってますか?
間違った使い方してませんか?
2、天気予報の裏技・・・天気予報をカスタマイズする。
(1)何を見るべきか?
①予報文を使うほうがいい・・・177番の意外な情報量
電話の177番や、ラジオの天気予報では、「南の風 日中 北の風 晴れ」なんていうお決まりの文句が使われていますが、これらは、各地の気象台が一日3回発表する予報の原文をそのまま読み上げたものです。

インターネットやテレビの天気予報では、地図上に天気マークが表示され、一目で天気の傾向が理解できますから、いまさら177番もないだろう・・・と思われるかもしれません。
では、「南西の風 後 南の風 雨 夜遅く くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雷 を伴う」という予報が発表された場合を考えてみましょう。
この予報を天気マークにすると、”雨のち曇り”のマークが表示されるだけです。

ところが、予報文だと、雨が曇りに変わるタイミングが「夜遅く」であることや、場所によっては夕方以降も「雷」があることまで知ることができるのです。
さらに、風の予報にいたっては、インターネットでは風の予報の画面に切り替えなければなりませんし、テレビの天気予報では、画面に表示したり、コメントしてくれなければそれまでです。
もっとも、ネットの天気予報で流行のピンポイント予報を見れば、「夜遅く」や「夜のはじめ頃 まで 雷 を伴う」という部分もわかるじゃん?と思われるかもしれません。

たしかにピンポイント予報があれば、「夜遅く」の部分はある程度わかるにせよ、「所により・・・雷を伴う」がわからないのです。
そもそも、ピンポイント予報の天気マークに雷マークが存在していない場合が多い。
これ、コンピューターで作る予報では雷を予測できないからです。
仮に雷予測ができたとしても、または手入力で雷予測が加わったとしてもダメ。
たとえば、”ピンポイント”予報で雷が予想されていなかったとしても、お隣の”ピンポイント”・・・となり町かもしれません・・・で雷が予想されているかもしれない・・・ということがあるのです。
つまり、「所により」の所を自分で探さなければならない・・・・いいかえれば、ほんのわずか距離で雷の予想がズレただけで、想像もしていなかった雷に遭うこともありうるのです。
これは、ピンポイントが、より細かなピンポイントであればあるほど起こりうる、いわばデジタル思考の矛盾といえましょう。
どうです?電話の177番の情報量の多さ・・・・すごいと思いませんか?
②いまさら177番
電話の177番がどれだけスゴイのかおわかりいただけたと思いますが、いまさら・・・・
続きは次の記事で
ご質問・御意見・ご要望がありましたらコメントお待ちしております。
どの情報を、いつ、どのように見ればよいのか・・・・知ってますか?
間違った使い方してませんか?
2、天気予報の裏技・・・天気予報をカスタマイズする。
(1)何を見るべきか?
①予報文を使うほうがいい・・・177番の意外な情報量
電話の177番や、ラジオの天気予報では、「南の風 日中 北の風 晴れ」なんていうお決まりの文句が使われていますが、これらは、各地の気象台が一日3回発表する予報の原文をそのまま読み上げたものです。

インターネットやテレビの天気予報では、地図上に天気マークが表示され、一目で天気の傾向が理解できますから、いまさら177番もないだろう・・・と思われるかもしれません。
では、「南西の風 後 南の風 雨 夜遅く くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雷 を伴う」という予報が発表された場合を考えてみましょう。
この予報を天気マークにすると、”雨のち曇り”のマークが表示されるだけです。

ところが、予報文だと、雨が曇りに変わるタイミングが「夜遅く」であることや、場所によっては夕方以降も「雷」があることまで知ることができるのです。
さらに、風の予報にいたっては、インターネットでは風の予報の画面に切り替えなければなりませんし、テレビの天気予報では、画面に表示したり、コメントしてくれなければそれまでです。
もっとも、ネットの天気予報で流行のピンポイント予報を見れば、「夜遅く」や「夜のはじめ頃 まで 雷 を伴う」という部分もわかるじゃん?と思われるかもしれません。

たしかにピンポイント予報があれば、「夜遅く」の部分はある程度わかるにせよ、「所により・・・雷を伴う」がわからないのです。
そもそも、ピンポイント予報の天気マークに雷マークが存在していない場合が多い。
これ、コンピューターで作る予報では雷を予測できないからです。
仮に雷予測ができたとしても、または手入力で雷予測が加わったとしてもダメ。
たとえば、”ピンポイント”予報で雷が予想されていなかったとしても、お隣の”ピンポイント”・・・となり町かもしれません・・・で雷が予想されているかもしれない・・・ということがあるのです。
つまり、「所により」の所を自分で探さなければならない・・・・いいかえれば、ほんのわずか距離で雷の予想がズレただけで、想像もしていなかった雷に遭うこともありうるのです。
これは、ピンポイントが、より細かなピンポイントであればあるほど起こりうる、いわばデジタル思考の矛盾といえましょう。
どうです?電話の177番の情報量の多さ・・・・すごいと思いませんか?
②いまさら177番
電話の177番がどれだけスゴイのかおわかりいただけたと思いますが、いまさら・・・・
続きは次の記事で
ご質問・御意見・ご要望がありましたらコメントお待ちしております。
2009年11月07日
天気予報のチェック方法(3)
前の記事を読むにはココをクリック
②いまさら177番・・・ネットで177番?
電話の177番がスゴイ!ということがおわかりいただけたと思いますが、ネット社会の現代ではちょっと古いような気がします。また、耳だけで情報を入手できるという点ではすぐれているものの、文字情報の必要性も感じます。
そこで、気象庁発表の予報文をネットで見ることができるのか?
不思議なことに、気象庁発表の予報文をそのまま表示してくれるサイトはなかなかないのです。
Kasayanが知っている唯一予報文をまるごと表示してくれるのが国際気象海洋のサイト。
http://www.dab.hi-ho.ne.jp/kasayan/kasayanflame.htm
トップページの「府県天気予報文」がそれ。
http://www.imocwx.com/yohoud.htm
これを丸ごと読めば、自家製の177番になります。
また、地方ローカル局のテレビやラジオの天気予報番組も、予報文の末尾に「・・になる見込みです」とか「・・・となるでしょう」という言葉をつけているだけですから、これを見ればまともな解説のついていないテレビやラジオの天気予報番組は不要になりますよね。

それでは、気象庁のサイトはどうなっているでしょうか?
残念ながら発表もとの気象庁のサイトでさえ、天気マーク付きの表に加工してしまっています。
まったく余計なことをしてくれるものですが、、予報文に書かれている文字情報はほぼ網羅していますから、使う上で問題はないと思います。
http://www.jma.go.jp/jp/yoho/322.html

それでは外出先で携帯を使った場合は何を見れば良いのでしょうか?
残念ながら予報文をまるごと表示してくれるサイトをKasayanは見たことがありません。
知っている方がいらっしゃったらぜひ教えてほしいのですが・・・・携帯なんだから177にかければ良いのでは?
(2)どうやって使うのか?
①予報文を読むためのルール
気象庁発表の予報の最終製品である予報文ですが、これを読むには簡単なルールがあります。
このルールを知っておくだけで、予報文をさらに情報量の多いものにすることができます。
では、予報文を・・・・・
続きは次の記事で・・・
ご意見、ご質問等ありましたらコメントしてください。
②いまさら177番・・・ネットで177番?
電話の177番がスゴイ!ということがおわかりいただけたと思いますが、ネット社会の現代ではちょっと古いような気がします。また、耳だけで情報を入手できるという点ではすぐれているものの、文字情報の必要性も感じます。
そこで、気象庁発表の予報文をネットで見ることができるのか?
不思議なことに、気象庁発表の予報文をそのまま表示してくれるサイトはなかなかないのです。
Kasayanが知っている唯一予報文をまるごと表示してくれるのが国際気象海洋のサイト。
http://www.dab.hi-ho.ne.jp/kasayan/kasayanflame.htm
トップページの「府県天気予報文」がそれ。
http://www.imocwx.com/yohoud.htm
これを丸ごと読めば、自家製の177番になります。
また、地方ローカル局のテレビやラジオの天気予報番組も、予報文の末尾に「・・になる見込みです」とか「・・・となるでしょう」という言葉をつけているだけですから、これを見ればまともな解説のついていないテレビやラジオの天気予報番組は不要になりますよね。

それでは、気象庁のサイトはどうなっているでしょうか?
残念ながら発表もとの気象庁のサイトでさえ、天気マーク付きの表に加工してしまっています。
まったく余計なことをしてくれるものですが、、予報文に書かれている文字情報はほぼ網羅していますから、使う上で問題はないと思います。
http://www.jma.go.jp/jp/yoho/322.html

それでは外出先で携帯を使った場合は何を見れば良いのでしょうか?
残念ながら予報文をまるごと表示してくれるサイトをKasayanは見たことがありません。
知っている方がいらっしゃったらぜひ教えてほしいのですが・・・・携帯なんだから177にかければ良いのでは?
(2)どうやって使うのか?
①予報文を読むためのルール
気象庁発表の予報の最終製品である予報文ですが、これを読むには簡単なルールがあります。
このルールを知っておくだけで、予報文をさらに情報量の多いものにすることができます。
では、予報文を・・・・・
続きは次の記事で・・・
ご意見、ご質問等ありましたらコメントしてください。
2009年11月10日
天気予報のチェック方法(4)
正しく天気予報をチェックしていますか?
「晴れのち曇り」という予報の「のち」とは何時?を指すのですか?
正しくチェックすれば、何倍も役立つ天気予報!
この「天気予報の使い方」カテゴリーでは、天気予報の正しいチェック方法、裏技をお伝えしています。
(2)どうやって使うのか?
①予報文を読むためのルール
レトロな感じがする気象庁発表の予報文が、一見わかりやすいように感じられる天気マークの天気予報の何倍もの情報量をもっていること、それをどうやって入手するか、おわかりいただけたかと思います。

いわば、予報文は一般向けの天気予報の最終製品といえますが、ただ漠然と読んでいても用語の裏に隠された貴重な情報を逃すことになります。
なぜなら、予報文に使われている用語は一定のルール(定義)にもとづいて使われていて、ルールに従って予報文を読めば、「時々」とはどの程度の状態を指すのか?、「のち」とは何時のことなのか?などを知ることができるからです。
ただでさえ情報量の多い予報文の骨の髄までしゃぶりつくすために、一度はこのルールに目を通しておくことをお勧めします。
では、ある日の予報文をもう一度よく見てみましょう。
書かれている文字ごとにルールを見ていきます。
【「北部」】
これが予報の対象エリアを指していることは当然ですが、正式には「府県予報区」の「一次細分区域」といいます。
自分が住んでいるエリアは天気予報のどのエリアに属しているかはご存じだと思いますが、主要都市ならいざしらず、区分の境界エリアについては案外あいまいなものです。
たとえば、長野市が「北部」であることは容易に察せられますが、坂城町は「北部」、それとも「中部」のいずれに属するのでしょうか?
また、辰野町は「中部」、「南部」のいずれでしょうか?
このように、県内の小旅行のために天気予報をチェックする場合ですら、自分の住んでいるエリアを少し離れるだけで、予報のエリアを知らないものだと痛感させられます。
そこで、必要なエリアの天気予報をチェックするために、予報の区分を確認しておきたいものです。
ココをクリックすると予報区分が表示されます(PDFファイル)

また、予報区分を知っておけば、区分の境界エリアの天気をチェックする際に、二つの区分の天気を両方チェックして、悪いほうの予報・・・たとえば夕方の雷の予想が、もう一方の区分にも影響するかもしれないこと・・・をあらかじめ予測しておくことも可能です。
特に県境では、地形などの影響もあって、隣接県の隣接予報区分の天気予報のほうが、そのエリアの天気に合致する場合も多いですから、隣接県の予報をチェックすることも大変有効です。
この点、昔は隣接県のテレビ番組を見ることができないという問題もありましたが、ネットで天気予報をチェックできるようになった現在では特に有効な手段でしょう。
【「夜のはじめ頃」】
この用語が、天気予報に登場したのは2007年から。
それまでは「宵のうち」という用語がつかわれていましたが、示す対象時間帯がわかりにくいということで変更されました。
とはいっても、夜のはじめというイメージも夏と冬で2時間程度も異なりますから、あいかわらずわかりにくい表現。
これについても、当然に気象庁のルールがあります。
続きは次の記事で・・・・
「晴れのち曇り」という予報の「のち」とは何時?を指すのですか?
正しくチェックすれば、何倍も役立つ天気予報!
この「天気予報の使い方」カテゴリーでは、天気予報の正しいチェック方法、裏技をお伝えしています。
(2)どうやって使うのか?
①予報文を読むためのルール
レトロな感じがする気象庁発表の予報文が、一見わかりやすいように感じられる天気マークの天気予報の何倍もの情報量をもっていること、それをどうやって入手するか、おわかりいただけたかと思います。

いわば、予報文は一般向けの天気予報の最終製品といえますが、ただ漠然と読んでいても用語の裏に隠された貴重な情報を逃すことになります。
なぜなら、予報文に使われている用語は一定のルール(定義)にもとづいて使われていて、ルールに従って予報文を読めば、「時々」とはどの程度の状態を指すのか?、「のち」とは何時のことなのか?などを知ることができるからです。
ただでさえ情報量の多い予報文の骨の髄までしゃぶりつくすために、一度はこのルールに目を通しておくことをお勧めします。
では、ある日の予報文をもう一度よく見てみましょう。
北部
今日 南東の風 晴れ 昼過ぎ から 夕方 くもり (101)
明日 南東の風 晴れ 昼過ぎ から くもり 所により
夕方 から 夜のはじめ頃 雨 (111)
明後日 北の風 後 南西の風 くもり (200)
書かれている文字ごとにルールを見ていきます。
【「北部」】
これが予報の対象エリアを指していることは当然ですが、正式には「府県予報区」の「一次細分区域」といいます。
自分が住んでいるエリアは天気予報のどのエリアに属しているかはご存じだと思いますが、主要都市ならいざしらず、区分の境界エリアについては案外あいまいなものです。
たとえば、長野市が「北部」であることは容易に察せられますが、坂城町は「北部」、それとも「中部」のいずれに属するのでしょうか?
また、辰野町は「中部」、「南部」のいずれでしょうか?
このように、県内の小旅行のために天気予報をチェックする場合ですら、自分の住んでいるエリアを少し離れるだけで、予報のエリアを知らないものだと痛感させられます。
そこで、必要なエリアの天気予報をチェックするために、予報の区分を確認しておきたいものです。
ココをクリックすると予報区分が表示されます(PDFファイル)

また、予報区分を知っておけば、区分の境界エリアの天気をチェックする際に、二つの区分の天気を両方チェックして、悪いほうの予報・・・たとえば夕方の雷の予想が、もう一方の区分にも影響するかもしれないこと・・・をあらかじめ予測しておくことも可能です。
特に県境では、地形などの影響もあって、隣接県の隣接予報区分の天気予報のほうが、そのエリアの天気に合致する場合も多いですから、隣接県の予報をチェックすることも大変有効です。
この点、昔は隣接県のテレビ番組を見ることができないという問題もありましたが、ネットで天気予報をチェックできるようになった現在では特に有効な手段でしょう。
【「夜のはじめ頃」】
この用語が、天気予報に登場したのは2007年から。
それまでは「宵のうち」という用語がつかわれていましたが、示す対象時間帯がわかりにくいということで変更されました。
とはいっても、夜のはじめというイメージも夏と冬で2時間程度も異なりますから、あいかわらずわかりにくい表現。
これについても、当然に気象庁のルールがあります。
続きは次の記事で・・・・
2009年11月11日
天気予報のチェック方法(5)
正しく天気予報をチェックしていますか?
「晴れのち曇り」という予報の「のち」とは何時?を指すのですか?
正しくチェックすれば、何倍も役立つ天気予報!
「天気予報の使い方」カテゴリーでは、天気予報の正しいチェック方法、裏技をお伝えしています。
【「夜のはじめ頃」】
この用語が、天気予報に登場したのは2007年から。
それまでは「宵のうち」という用語がつかわれていましたが、示す対象時間帯がわかりにくいということで変更されました。
とはいっても、夜のはじめというイメージも夏と冬で2時間程度も異なりますから、あいかわらずわかりにくい表現。
これについても、当然に気象庁のルールがあります。

表を見て気付かれたと思いますが、驚くことに時間に関する用語だけで一日を3時間単位ですべて表現してしまっています。
いわゆる「時系列予報」と呼ばれる予報のほとんどは3時間とごの天気を表にして表現していますが、文字だけの予報文も、それと同等の時系列性を確保しているといってよいでしょう。
むしろ、時系列予報の内容は、視覚にうったえるものであるだけに全部覚えておくことは困難ですが、予報文は簡単に覚えておくことができるという点で、お天気チェックに使う情報の主体は予報文にして、時系列予報を補助的に使うという位置づけにすべきです。
続きは次の記事で・・・・・
「晴れのち曇り」という予報の「のち」とは何時?を指すのですか?
正しくチェックすれば、何倍も役立つ天気予報!
「天気予報の使い方」カテゴリーでは、天気予報の正しいチェック方法、裏技をお伝えしています。
【「夜のはじめ頃」】
この用語が、天気予報に登場したのは2007年から。
それまでは「宵のうち」という用語がつかわれていましたが、示す対象時間帯がわかりにくいということで変更されました。
とはいっても、夜のはじめというイメージも夏と冬で2時間程度も異なりますから、あいかわらずわかりにくい表現。
これについても、当然に気象庁のルールがあります。

表を見て気付かれたと思いますが、驚くことに時間に関する用語だけで一日を3時間単位ですべて表現してしまっています。
いわゆる「時系列予報」と呼ばれる予報のほとんどは3時間とごの天気を表にして表現していますが、文字だけの予報文も、それと同等の時系列性を確保しているといってよいでしょう。
むしろ、時系列予報の内容は、視覚にうったえるものであるだけに全部覚えておくことは困難ですが、予報文は簡単に覚えておくことができるという点で、お天気チェックに使う情報の主体は予報文にして、時系列予報を補助的に使うという位置づけにすべきです。
続きは次の記事で・・・・・
2009年11月12日
天気予報のチェック方法(6)
正しく天気予報をチェックしていますか?
「晴れのち曇り」という予報の「のち」とは何時?を指すのですか?
正しくチェックすれば、何倍も役立つ天気予報!
「天気予報の使い方」カテゴリーでは、天気予報の正しいチェック方法、裏技をお伝えしています。
【「晴れ」「曇り」「雨」】
予報文の中で、もっとも読み流してしまいがちな用語でしょう。
しかし、日常用語として各人が勝手に解釈し、空模様をイメージしてしまいますから、ちょっと困りものの用語です。
一度でも用語の定義を読んで自分なりのイメージを作っておくと、予報文をより正確に読むことができると思います。
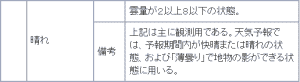
まず、「晴れ」の定義ですが、なんとなく理解できます。
「薄曇り」で地物の影ができる状態、というのがちょっと面白いですね。
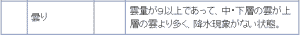
曇りの定義は、筋雲(卷雲)やうろこ雲(卷層雲)などの高層雲よりも、ひつじ雲(高積雲)などの中層雲や、わた雲(積雲)や入道雲(積乱雲)などの下層雲が支配的な場合を指しています。
晴れの定義から考えて、影ができない程度に曇った場合と考えたらイメージしやすいかもしれません。

雨はその降り方によって様々な表現が使われます。
予報文に「強く降る」と書かれていたら、時間雨量が20~30ミリ程度が予想されているということですから、いわゆる”どしゃ降り”のイメージ。また、「激しく降る」と書かれていたら30~50ミリの”バケツをひっくり返したような雨”、「非常に激しく降る」ならば”滝のような雨”をイメージします。
天気図を解析して番組の解説原稿を書くときも、この用語を正確に使うよう注意されましたが、解説者によってはかなりいい加減に使っていたりします。
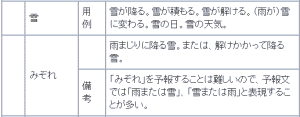
雪については、天気予報の現場にいても意識したことはありませんでした。
むしろ、何センチ積もるのか?という点が重要。
何センチ積もるのか?については予報文に書かれませんから別に調べる必要があります。
このように天気の用語も厳格に定義づけられていますが、目で確認できる雨や雲ひとつない快晴以外、晴れと曇りのイメージは人によって千差万別です。
この定義に照らして、一度はイメージづくりをしておいても良いかもしれませんね。
続きは次の記事で・・・・
「晴れのち曇り」という予報の「のち」とは何時?を指すのですか?
正しくチェックすれば、何倍も役立つ天気予報!
「天気予報の使い方」カテゴリーでは、天気予報の正しいチェック方法、裏技をお伝えしています。
【「晴れ」「曇り」「雨」】
予報文の中で、もっとも読み流してしまいがちな用語でしょう。
しかし、日常用語として各人が勝手に解釈し、空模様をイメージしてしまいますから、ちょっと困りものの用語です。
一度でも用語の定義を読んで自分なりのイメージを作っておくと、予報文をより正確に読むことができると思います。
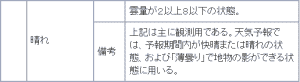
まず、「晴れ」の定義ですが、なんとなく理解できます。
「薄曇り」で地物の影ができる状態、というのがちょっと面白いですね。
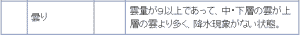
曇りの定義は、筋雲(卷雲)やうろこ雲(卷層雲)などの高層雲よりも、ひつじ雲(高積雲)などの中層雲や、わた雲(積雲)や入道雲(積乱雲)などの下層雲が支配的な場合を指しています。
晴れの定義から考えて、影ができない程度に曇った場合と考えたらイメージしやすいかもしれません。

雨はその降り方によって様々な表現が使われます。
予報文に「強く降る」と書かれていたら、時間雨量が20~30ミリ程度が予想されているということですから、いわゆる”どしゃ降り”のイメージ。また、「激しく降る」と書かれていたら30~50ミリの”バケツをひっくり返したような雨”、「非常に激しく降る」ならば”滝のような雨”をイメージします。
天気図を解析して番組の解説原稿を書くときも、この用語を正確に使うよう注意されましたが、解説者によってはかなりいい加減に使っていたりします。
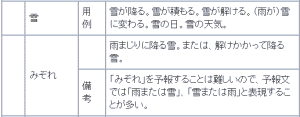
雪については、天気予報の現場にいても意識したことはありませんでした。
むしろ、何センチ積もるのか?という点が重要。
何センチ積もるのか?については予報文に書かれませんから別に調べる必要があります。
このように天気の用語も厳格に定義づけられていますが、目で確認できる雨や雲ひとつない快晴以外、晴れと曇りのイメージは人によって千差万別です。
この定義に照らして、一度はイメージづくりをしておいても良いかもしれませんね。
続きは次の記事で・・・・
2009年11月13日
天気予報のチェック方法(7)
正しく天気予報をチェックしていますか?
「晴れのち曇り」という予報の「のち」とは何時?を指すのですか?
正しくチェックすれば、何倍も役立つ天気予報!
「天気予報の使い方」カテゴリーでは、天気予報の正しいチェック方法、裏技をお伝えしています。
【「のち」「一時」「時々」】
「のち」辞書によれば「連続するものの中で、次にくるもの」を指します。
でも「次」はいつくるんでしょうか?
用語集を見ると「予報期間内の前と後で現象が異なるとき、その変化を示すときに用いる。 」んだそうです。
そして、「「・・・ のち ・・・」は大局的な傾向を表す用語であるから可能な限り用いないで、具体的な時間帯を示すように努める。 」んだそうです。
ということは、”次はいつくるのか?”ということをしっかりと予報文に書けってこと。
ですから、「・・・のち・・・」しかわからない天気マークの予報だけ見ていたら、苦労している気象台の予報官に失礼?ってことになりますね。

もっとも例外があって、「時間帯を示す用語が2つになる時は一方に「のち」を用いる。その際の時間指定は降水現象を優先する。例えば「晴れ昼すぎから曇り夕方から雨」とはせずに「晴れのち曇り夕方から雨」などとする。 」んだそうです。
また、「具体的な時間帯を示す精度がない場合は「のち」を用いてもよい」んだそうですから、天気変化の時間帯を特定できない場合にも使われるようです。
同様に「一時」「時々」という用語も厳格なルールに従って使われています。
これらの用語を簡単にまとめた表がこれです。

なにげに聞き流してしまう「後」「一時」「時々」などの天気変化の用語ですけど、天気の変わり目のタイミングや天気の様子を伝えてくれる重要な用語です。
これを使いこなさない手はありませんから、一度はフムフムと読んでみてください。
続きは次の記事で・・・・・
「晴れのち曇り」という予報の「のち」とは何時?を指すのですか?
正しくチェックすれば、何倍も役立つ天気予報!
「天気予報の使い方」カテゴリーでは、天気予報の正しいチェック方法、裏技をお伝えしています。
【「のち」「一時」「時々」】
「のち」辞書によれば「連続するものの中で、次にくるもの」を指します。
でも「次」はいつくるんでしょうか?
用語集を見ると「予報期間内の前と後で現象が異なるとき、その変化を示すときに用いる。 」んだそうです。
そして、「「・・・ のち ・・・」は大局的な傾向を表す用語であるから可能な限り用いないで、具体的な時間帯を示すように努める。 」んだそうです。
ということは、”次はいつくるのか?”ということをしっかりと予報文に書けってこと。
ですから、「・・・のち・・・」しかわからない天気マークの予報だけ見ていたら、苦労している気象台の予報官に失礼?ってことになりますね。

もっとも例外があって、「時間帯を示す用語が2つになる時は一方に「のち」を用いる。その際の時間指定は降水現象を優先する。例えば「晴れ昼すぎから曇り夕方から雨」とはせずに「晴れのち曇り夕方から雨」などとする。 」んだそうです。
また、「具体的な時間帯を示す精度がない場合は「のち」を用いてもよい」んだそうですから、天気変化の時間帯を特定できない場合にも使われるようです。
同様に「一時」「時々」という用語も厳格なルールに従って使われています。
これらの用語を簡単にまとめた表がこれです。

なにげに聞き流してしまう「後」「一時」「時々」などの天気変化の用語ですけど、天気の変わり目のタイミングや天気の様子を伝えてくれる重要な用語です。
これを使いこなさない手はありませんから、一度はフムフムと読んでみてください。
続きは次の記事で・・・・・
2009年11月14日
天気予報のチェック方法(8)
正しく天気予報をチェックしていますか?
「晴れのち曇り」という予報の「のち」とは何時?を指すのですか?
正しくチェックすれば、何倍も役立つ天気予報!
「天気予報の使い方」カテゴリーでは、天気予報の正しいチェック方法、裏技をお伝えしています。
【所により】
気象庁発表の予報の読み方のルールを簡単にまとめてきましたが、最後は「所により」。
なんともあいまいな表現ですが、散発的に雨が降ったりする場合には、どうしても場所を特定できませんから、この用語をなくすことは困難でしょう。
しかし、「所により」が使われるとき、自分の頭上が「所」になってしまった場合、その人はたいていの場合予報が外れたと感じてしまうのでやっかいです。
「所により」は天気マークに表現されていません。
テレビの天気予報でも解説の中でキチンとコメントされていない限り、所によっては雨が降る?なんてわかりません。ましてやネットで天気マークの予報だけ見たら、天気マークの裏に隠されている「所によって雨」なんて絶対に知ることができないでしょう。
天気マークしか見ていない人の頭上が「所」になったら、その人は予報がハズレたと思うに違いありませんね。
以前書いたように、天気マークの予報より、177番のような予報文の予報のほうがイイという理由がおわかりいただけると思います。

このほか「山沿い」という用語がつかわれる場合があります。
なんとなく、山の近くなんだな・・・ということはわかりますが、長野県のように山ばっかりのところでは、どこが山沿いなんだ?といいたくなります。
これも、しっかりとルールが決まっています。
長野地方気象台のHPによれば、
と書いてあります。
ですから、自分の家が山沿いにあるからといって予報の対象になっているわけではありません。
(2)いつ使うのか?
予報を読むためのルールがわかりましたが、いつ(何時)使うのか?がまた問題になります。
最新の予報で確認しましょう・・・・ということは感覚的にわかるのですが・・・・・・・
続きは次の記事で・・・・・
「晴れのち曇り」という予報の「のち」とは何時?を指すのですか?
正しくチェックすれば、何倍も役立つ天気予報!
「天気予報の使い方」カテゴリーでは、天気予報の正しいチェック方法、裏技をお伝えしています。
【所により】
気象庁発表の予報の読み方のルールを簡単にまとめてきましたが、最後は「所により」。
なんともあいまいな表現ですが、散発的に雨が降ったりする場合には、どうしても場所を特定できませんから、この用語をなくすことは困難でしょう。
しかし、「所により」が使われるとき、自分の頭上が「所」になってしまった場合、その人はたいていの場合予報が外れたと感じてしまうのでやっかいです。
「所により」は天気マークに表現されていません。
テレビの天気予報でも解説の中でキチンとコメントされていない限り、所によっては雨が降る?なんてわかりません。ましてやネットで天気マークの予報だけ見たら、天気マークの裏に隠されている「所によって雨」なんて絶対に知ることができないでしょう。
天気マークしか見ていない人の頭上が「所」になったら、その人は予報がハズレたと思うに違いありませんね。
以前書いたように、天気マークの予報より、177番のような予報文の予報のほうがイイという理由がおわかりいただけると思います。

このほか「山沿い」という用語がつかわれる場合があります。
なんとなく、山の近くなんだな・・・ということはわかりますが、長野県のように山ばっかりのところでは、どこが山沿いなんだ?といいたくなります。
これも、しっかりとルールが決まっています。
長野地方気象台のHPによれば、
天気予報などにおける「山沿い」に含まれる地域について
天気予報で、「北部の山沿いは、曇り時々雪」などと表現されることがあります。
この「山沿い」は長野県北部の冬期間(11月頃~3月頃まで)の降雪のみを対象に使用し、「長野」の一部(長野市の一部(旧戸隠村・旧鬼無里村)、高山村の標高800m以上の地域、飯綱町、信濃町、小川村)及び「大町」の大部分(小谷村、白馬村、大町市の標高800m以上の地域)を「山沿い」と呼称します。
と書いてあります。
ですから、自分の家が山沿いにあるからといって予報の対象になっているわけではありません。
(2)いつ使うのか?
予報を読むためのルールがわかりましたが、いつ(何時)使うのか?がまた問題になります。
最新の予報で確認しましょう・・・・ということは感覚的にわかるのですが・・・・・・・
続きは次の記事で・・・・・


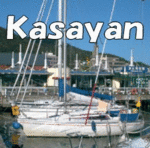


 はてなに追加
はてなに追加 MyYahoo!に追加
MyYahoo!に追加 del.icio.usに追加
del.icio.usに追加 livedoorClipに追加
livedoorClipに追加




