2011年07月19日
台風6号予想進路と風や雨の様子(7月19日)
台風6号も今日からが本番といったところ。
テレビでは天気予報だけでなく、ニュースでもトップ項目に挙がるようになっています。
「台風が大型で勢力が強く、速度が遅いから西日本(四国方面)中心に荒天が長時間続き、台風に先行して東日本でも南岸中心に大雨が継続するから注意して」という話が、どのチャンネル、どの番組でも聞かれるはずですから、Kasayanのブログでは、テレビの天気予報では放送してくれない情報にこだわってまとめていきたいと思います。
まず、台風の予想進路図ですが、3時間毎に更新されてしまいますから、書きっぱなしのブログに引用するのは好ましくありません。
速度が遅いため、フラフラと進みそうな台風6号の予想コースをチェックするには、更新頻度の多い気象庁のHPの予想進路図を主にして、米軍の予想進路図をセカンドオピニオンとして使うのが効果的な使い方だと思います。
気象庁進路予想図: http://www.jma.go.jp/jp/typh/110624d.html
米軍進路予想図: http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp0811.gif
(米軍進路予想図(JTWC)の表示時間は世界標準時なので、+9時間してください)
では、気象庁の通常の予報の中核に位置するGSMというシミュレーションモデルの計算結果を使って、明後日(21日)にかけての台風の位置、雨と風の様子をチェックしてみましょう。
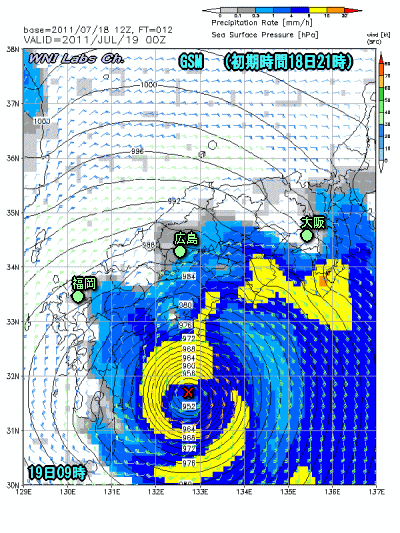
色塗りは1時間降水量で、青<黄色<オレンジの順で降水量(mm/h)が多いことを意味しています。また、風向風速は矢ばねで表示されており、青<黄緑<緑の順で風速が強いことを意味します。(図左スケールの風速はノット表示。1/2にするとm/sになります)。
反時計回りに風が台風に吹き込み、風が陸にぶつかる台風の東~北東側の太平洋沿岸で降水量が多く計算されていることがわかると思います。
(あなたの頭上の風や雨は今後どのように変化するでしょうか?読みとってみましょう)
また、昨夜21時の観測値にもとづいて計算されたこの計算値では、高知県東部に上陸し、徳島県方面を経由して紀伊半島南部に南下することを示唆していますが、これは今朝の気象庁発表の予想進路図とほぼ一致しています。
次に、気象庁が防災用と位置付けている解像度の高いMSMという別の計算値で、同じく今日から明日(20日)朝にかけての様子をチェックしてみましょう。
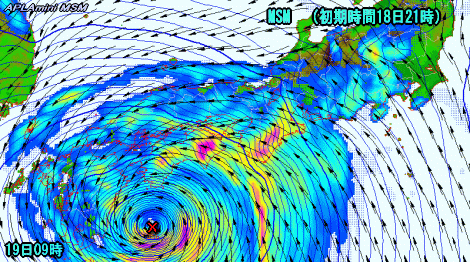
GSMモデルと同様、台風の速度が非常に遅く、明日朝になっても四国付近に台風が位置していることが分かります。
もっとも、台風の上陸地点が足摺岬付近、瀬戸内海を通過する点がGSMモデルと異なっています。
気象庁では台風専用のシミュレーションモデルを使い、統計的手法も用いて予想進路図を発表していますが、台風の速度が遅く計算値が多少ふらつく現状では、MSMモデルのように進むことも十分に考えられます。
どちらかにしてくれ・・・と思われるかもしれませんが、雨の予想については大勢に影響はありません(風上斜面は多少変化しますが)。
ただ、風向については場所によって(四国南岸?)台風の中心がどこを進むのかで180度変わってきますから。特に高潮に関しては発生しやすい場所も変化します。湾口が風上に開いていないからといって安心せずに安全マージンをとった対策が必要でしょう(そもそも誤差範囲を考慮した予報円内の話ではありますが)。
このように計算値がバラツクのは、自転車をゆっくり走らせるとハンドルがグラグラしてしまうのと同様、台風の速度が遅いということが原因です。
では、なぜ台風の速度が遅いのでしょう?・・・台風を東に流す上空の早い流れと台風の位置関係を、今日のデータで立体図にしてみました。
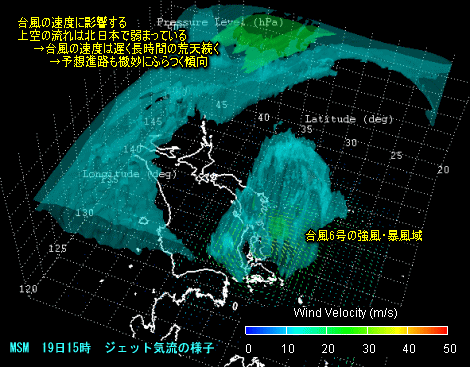
台風の強風・暴風エリアが北日本を流れる強い流れから孤立しています。
北日本にわずかに張り出した太平洋高気圧に北上を遮られ、日本の東側にある上空の低気圧の流れに乗るまでは、太平洋高気圧縁辺の弱い流れにノロノロと流されることになるからです。
(Uターンするように南下する理由については、太平洋高気圧との関係について昨日の記事参照)
ノロノロと四国付近を進むと四国付近の降水量が急激に増えてきます。
なぜ、四国や本州太平洋岸で雨が多くなるのか?・・・雨の原料・・・暖かく湿った空気の様子をチェック。
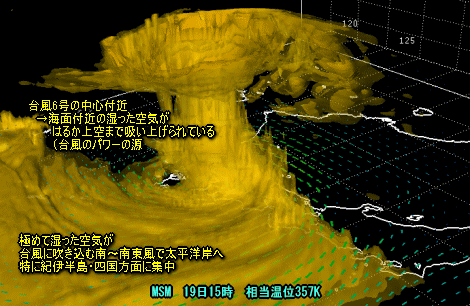
暖かく湿った空気が、まるで竜巻のように湿った空気が渦を巻いて太平洋岸に流れ込んでいるから・・・ですね。
最後は、昨日同様、今朝の実況データを用いながら、台風チェックに多用するであろう気象レーダーやアメダスの効果的なチェック方法をまとめておきました。
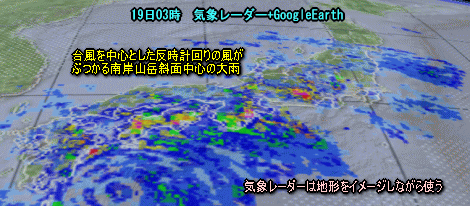
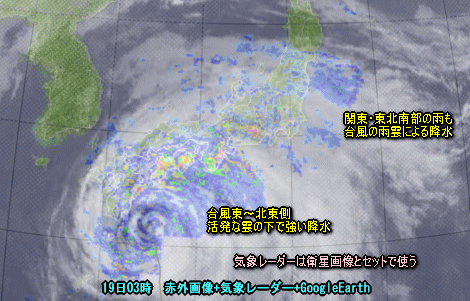
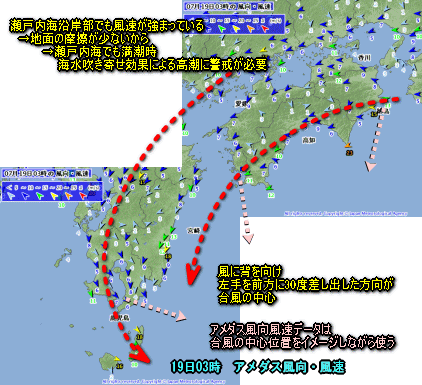
各データの使い方を図中に書き込んでおきましたが、オススメのHPはやはり気象庁のHPです。
見易さはもちろん、重要なのはデータの更新時間が明記され、読み方までレクチャーしてくれています。
最新のデータを正しく読むという基本を守るためには、他の情報の追随を許さないといってイイと言ってよいでしょう。
気象庁HP: http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
積算雨量:http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/pre_rct/index24_rct.html
降水量・強風等の詳細情報(文章): http://www.jma.go.jp/jp/typh/typh_text.html
自分で実況を把握したあと、上のアニメなどで雨の降り方や風の変化を予想される方も多いと思いますが、そんなときは必ず地元の気象台の予報官の頭の中(予報文)と比較してください。
予報官は、計算のふらつきや、安全マージンもしっかりと考慮して予想をしているからです。
予報文:http://www.imocwx.com/yohoud.htm
様々のデータをチェックするのはイイことですが、それだけではデータを生かすことができません。
総合的に考える・・・・難しそうですけど、それぞれのデータが互いに発生している現象の理由になっていると思いながらチェックすると新たな発見があるはずですよ。
今日も状況の変化などに気付いたら、不定期にこの記事に追記をしていきたいと思います。
19日03時40分発表 短期予報解説資料抜粋
「①台風第6号は、発達のピークを過ぎているが、この後も強い勢力を維持しながら、19日夜には、西日本太平洋側に接近・上陸する見込み。台風の北上に伴い西日本の太平洋側では、猛烈な風(四国沿岸40m/s)が吹き、西日本太平洋岸・東海では猛烈なしけとなる見込み。暴風や高波に厳重な警戒が必要。20 日には、台風は進路を東にかえて本州南岸を進む見込み。東日本でも、暴風や高波に警戒が必要。速度が遅いため、西日本・東日本では長時間台風の影響を受ける。
②東日本太平洋側では、20 日にかけて台風の外側をまわる暖湿気の流入し、地形性効果による降水が継続して降水量が多くなる。西日本では、台風本体の発達した雨雲もかかり、20 日にかけて1 時間80ミリを超える猛烈な雨が降るおそれがあり、降水量が更に多くなり大雨による低地の浸水、土砂災害、河川の増水やはん濫に警戒。また、台風が接近する時、やや離れた所で竜巻などの突風が発生することも多く、発達した対流雲周辺では注意が必要。
③西日本太平洋側では、19 日には満潮時を中心に高潮に注意・警戒が必要。20 日は東日本太平洋側でも高潮のおそれがある。」
| 10時20分追記 四国・紀伊半島中心の強雨になっていますが、関東北部でもまとまった雨になっています。 湿った空気がぶつかり強制上昇する地形効果がよく現れているので、レーダーとGoogleEarthを重ね合わせたものを掲載しておきます。レーダーとアメダスの風向風速データと組み合わせてチェックすると理解しやすいのではないでしょうか。  |
| 14時30分追記 足摺岬付近の台風6号の気象レーダー画像と、アメダス風向・風速データの関係。  |
| 19時15分追記 台風6号の予想進路が南東進する根拠。   |
ご意見・ご質問等は、コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。
可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)


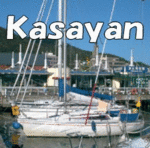


 はてなに追加
はてなに追加 MyYahoo!に追加
MyYahoo!に追加 del.icio.usに追加
del.icio.usに追加 livedoorClipに追加
livedoorClipに追加




