2009年11月10日
天気予報のチェック方法(4)
正しく天気予報をチェックしていますか?
「晴れのち曇り」という予報の「のち」とは何時?を指すのですか?
正しくチェックすれば、何倍も役立つ天気予報!
この「天気予報の使い方」カテゴリーでは、天気予報の正しいチェック方法、裏技をお伝えしています。
(2)どうやって使うのか?
①予報文を読むためのルール
レトロな感じがする気象庁発表の予報文が、一見わかりやすいように感じられる天気マークの天気予報の何倍もの情報量をもっていること、それをどうやって入手するか、おわかりいただけたかと思います。

いわば、予報文は一般向けの天気予報の最終製品といえますが、ただ漠然と読んでいても用語の裏に隠された貴重な情報を逃すことになります。
なぜなら、予報文に使われている用語は一定のルール(定義)にもとづいて使われていて、ルールに従って予報文を読めば、「時々」とはどの程度の状態を指すのか?、「のち」とは何時のことなのか?などを知ることができるからです。
ただでさえ情報量の多い予報文の骨の髄までしゃぶりつくすために、一度はこのルールに目を通しておくことをお勧めします。
では、ある日の予報文をもう一度よく見てみましょう。
書かれている文字ごとにルールを見ていきます。
【「北部」】
これが予報の対象エリアを指していることは当然ですが、正式には「府県予報区」の「一次細分区域」といいます。
自分が住んでいるエリアは天気予報のどのエリアに属しているかはご存じだと思いますが、主要都市ならいざしらず、区分の境界エリアについては案外あいまいなものです。
たとえば、長野市が「北部」であることは容易に察せられますが、坂城町は「北部」、それとも「中部」のいずれに属するのでしょうか?
また、辰野町は「中部」、「南部」のいずれでしょうか?
このように、県内の小旅行のために天気予報をチェックする場合ですら、自分の住んでいるエリアを少し離れるだけで、予報のエリアを知らないものだと痛感させられます。
そこで、必要なエリアの天気予報をチェックするために、予報の区分を確認しておきたいものです。
ココをクリックすると予報区分が表示されます(PDFファイル)

また、予報区分を知っておけば、区分の境界エリアの天気をチェックする際に、二つの区分の天気を両方チェックして、悪いほうの予報・・・たとえば夕方の雷の予想が、もう一方の区分にも影響するかもしれないこと・・・をあらかじめ予測しておくことも可能です。
特に県境では、地形などの影響もあって、隣接県の隣接予報区分の天気予報のほうが、そのエリアの天気に合致する場合も多いですから、隣接県の予報をチェックすることも大変有効です。
この点、昔は隣接県のテレビ番組を見ることができないという問題もありましたが、ネットで天気予報をチェックできるようになった現在では特に有効な手段でしょう。
【「夜のはじめ頃」】
この用語が、天気予報に登場したのは2007年から。
それまでは「宵のうち」という用語がつかわれていましたが、示す対象時間帯がわかりにくいということで変更されました。
とはいっても、夜のはじめというイメージも夏と冬で2時間程度も異なりますから、あいかわらずわかりにくい表現。
これについても、当然に気象庁のルールがあります。
続きは次の記事で・・・・
「晴れのち曇り」という予報の「のち」とは何時?を指すのですか?
正しくチェックすれば、何倍も役立つ天気予報!
この「天気予報の使い方」カテゴリーでは、天気予報の正しいチェック方法、裏技をお伝えしています。
(2)どうやって使うのか?
①予報文を読むためのルール
レトロな感じがする気象庁発表の予報文が、一見わかりやすいように感じられる天気マークの天気予報の何倍もの情報量をもっていること、それをどうやって入手するか、おわかりいただけたかと思います。

いわば、予報文は一般向けの天気予報の最終製品といえますが、ただ漠然と読んでいても用語の裏に隠された貴重な情報を逃すことになります。
なぜなら、予報文に使われている用語は一定のルール(定義)にもとづいて使われていて、ルールに従って予報文を読めば、「時々」とはどの程度の状態を指すのか?、「のち」とは何時のことなのか?などを知ることができるからです。
ただでさえ情報量の多い予報文の骨の髄までしゃぶりつくすために、一度はこのルールに目を通しておくことをお勧めします。
では、ある日の予報文をもう一度よく見てみましょう。
北部
今日 南東の風 晴れ 昼過ぎ から 夕方 くもり (101)
明日 南東の風 晴れ 昼過ぎ から くもり 所により
夕方 から 夜のはじめ頃 雨 (111)
明後日 北の風 後 南西の風 くもり (200)
書かれている文字ごとにルールを見ていきます。
【「北部」】
これが予報の対象エリアを指していることは当然ですが、正式には「府県予報区」の「一次細分区域」といいます。
自分が住んでいるエリアは天気予報のどのエリアに属しているかはご存じだと思いますが、主要都市ならいざしらず、区分の境界エリアについては案外あいまいなものです。
たとえば、長野市が「北部」であることは容易に察せられますが、坂城町は「北部」、それとも「中部」のいずれに属するのでしょうか?
また、辰野町は「中部」、「南部」のいずれでしょうか?
このように、県内の小旅行のために天気予報をチェックする場合ですら、自分の住んでいるエリアを少し離れるだけで、予報のエリアを知らないものだと痛感させられます。
そこで、必要なエリアの天気予報をチェックするために、予報の区分を確認しておきたいものです。
ココをクリックすると予報区分が表示されます(PDFファイル)

また、予報区分を知っておけば、区分の境界エリアの天気をチェックする際に、二つの区分の天気を両方チェックして、悪いほうの予報・・・たとえば夕方の雷の予想が、もう一方の区分にも影響するかもしれないこと・・・をあらかじめ予測しておくことも可能です。
特に県境では、地形などの影響もあって、隣接県の隣接予報区分の天気予報のほうが、そのエリアの天気に合致する場合も多いですから、隣接県の予報をチェックすることも大変有効です。
この点、昔は隣接県のテレビ番組を見ることができないという問題もありましたが、ネットで天気予報をチェックできるようになった現在では特に有効な手段でしょう。
【「夜のはじめ頃」】
この用語が、天気予報に登場したのは2007年から。
それまでは「宵のうち」という用語がつかわれていましたが、示す対象時間帯がわかりにくいということで変更されました。
とはいっても、夜のはじめというイメージも夏と冬で2時間程度も異なりますから、あいかわらずわかりにくい表現。
これについても、当然に気象庁のルールがあります。
続きは次の記事で・・・・
Posted by kasayan at 19:59│Comments(0)
│天気予報の使い方








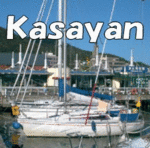


 はてなに追加
はてなに追加 MyYahoo!に追加
MyYahoo!に追加 del.icio.usに追加
del.icio.usに追加 livedoorClipに追加
livedoorClipに追加




