2011年08月15日
不安定な天気、北と南はまとまった雨(8月15日)
昨日の長野市内・・・・浸水被害や屋根のトタンが飛ぶような激しい雷雨が発生しました。
今日はどうなの?・・・ということで早速・・・・
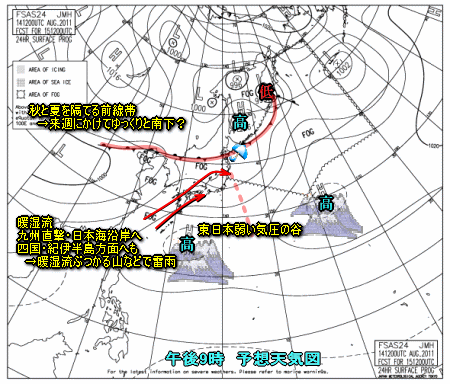
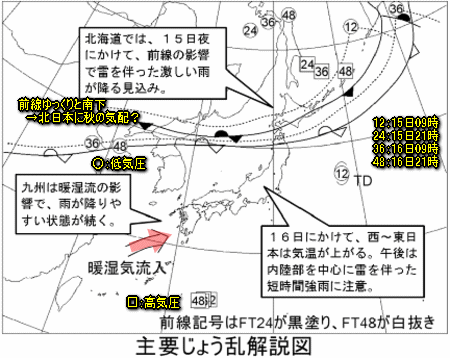
一言で言ってしまえば、昨日ほどではありませんけど、雷雨はある・・・ということです。
低気圧と前線に伴う北海道の雨は引き続き警戒が必要。
そして、雨の原料・・・暖湿流がモロに流れ込む九州の雨・・・・それも暖湿流がぶつかる九州西部の山岳西斜面でも引き続きまとまった雨に注意が必要です。
そんな様子を詳しく・・・・まずは、地上の天気の骨格・・・上空5800m付近の天気図から・・・・
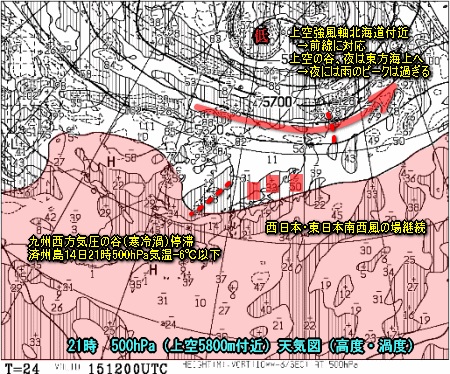
上空の天気図で見る太平洋高気圧は凹のカタチをしていて、九州の西側で弱い気圧の谷になっています。
この谷の上空には-6℃以下の寒気が入っていて、雨雲が高く成長しやすい状態。
地上付近に暖湿流が流れ込み雨雲が発生すれば、大雨必至という状態になっています。
一方、太平洋高気圧の勢力が及ばない北海道方面はしっかりとした気圧の谷になっていて、谷に南側にジェット気流。
この流れに沿って地上では前線が発生し、気圧の谷付近を低気圧が東へと進みます。
そして、太平洋高気圧の北の端っこにあたる東日本方面・・・
赤の■で塗った数字・・・渦度といいますが、+マークの部分では反時計回りの低気圧性の空気の渦が出来やすい場所。
昨日より数字が小さくなっていて、低気圧性の渦・・・上昇気流が出来やすさの程度・・・・雷雲が発生しやすさの程度も昨日よりやや低めといったところ。
では、雨の原料・・・暖湿流の様子。
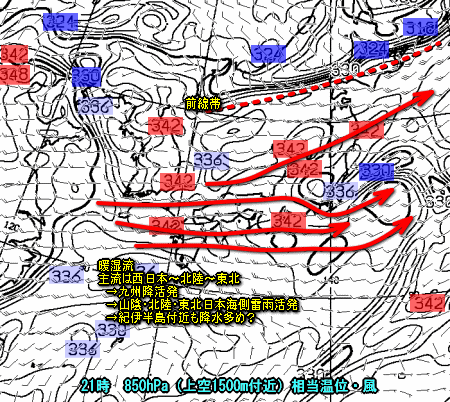
九州には真西から暖湿流が流入。
西斜面で大雨というイメージが沸きますよね。
九州を回り込むように流れる暖湿流が山陰や北陸、そして北海道方面へ流れ込みますから日本海沿岸付近も不安定な天気・・・雷雨の発生可能性は十分。
九州の南を回り込む暖湿流によって、紀伊半島方面でも雷雨になりますが、紀伊半島の風下にあたる中部や関東では、上空の渦度が低くなるということと相まって、昨日ほどの雷雨は発生しない・・・ということになりそうです・・・・計算値上は・・・・
それでは具体的に雨の様子を・・・・
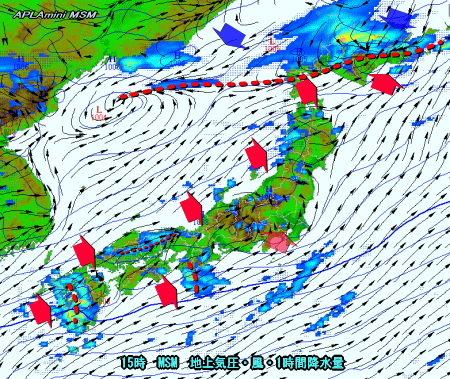
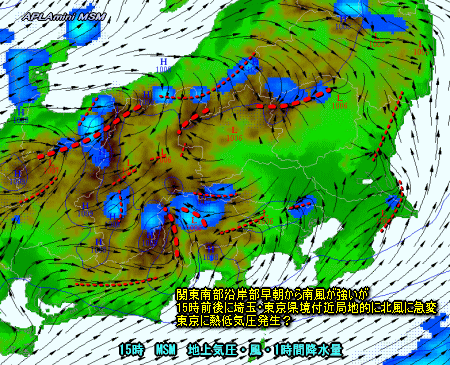
暖湿流の流れと雨の様子をイメージしやすいように全国の図には赤矢印を書き込んでおきました。
15時45分追記:書き込みを忘れてしまいましたが、関東甲信越地方で発生した雷雲は上空3000m付近の西~南西風に流されます。赤の点線の発生可能性エリアの北東側も要注意ということになります。
沿岸部を流れる暖湿流は海風によって内陸部に運び込まれますが、海風などの局地的な風は地形や内陸の暖まり方によってものすごく微妙。
関東甲信越方面の雷雨・・・・いつものように発生しそうなところに点線を引いてありますが、細い線で引いた、「やや可能性がある」「発生しても局地的」と思われる場所・・・・かなり怪しくなっています。
あくまで目安に・・・・・
東京都心部・・・・ちょっとアヤシイ風の流れになっているので・・・どの程度計算値を信じられるのか?イマイチわかりませんが、今日の着目点です。
気象庁レーダー(基本ツール): http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
河川情報センター(広域詳細チェック用): http://www.river.go.jp/
Xバンドレーダー(地域詳細チェック用): http://www.river.go.jp/xbandradar/
東京アメッシュ(地域限定詳細チェック用): http://tokyo-ame.jwa.or.jp/
【昨日(14日)の雷雨の様子】
昨日の雷雨では、Kasayanの住む長野市内でも被害が発生するほどの雷雨になりましたから、多少は詳しく書かなければ・・・
まずは、雷雨の発生に影響する風の収束のモト・・・風を支配する気圧配置から。
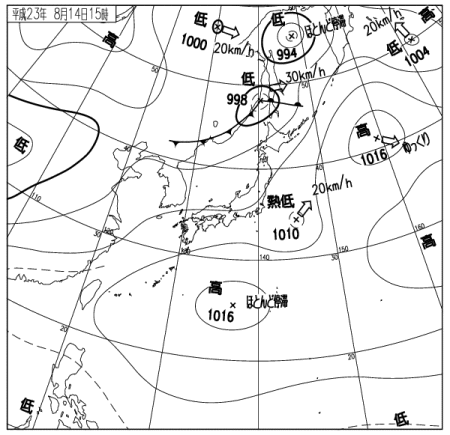
東日本は等圧線が太平洋高気圧側に凹になった弱い気圧の谷。
谷の真ん中にはずいぶん衰弱した熱帯低気圧があって北東に進んでいました。
ということは、日本海側を北海道の低気圧や前線に向かっていた暖湿流が日本海の海風に乗って内陸に流れ込みやすい状態。
同時刻の局地的な天気図を見ると・・・・
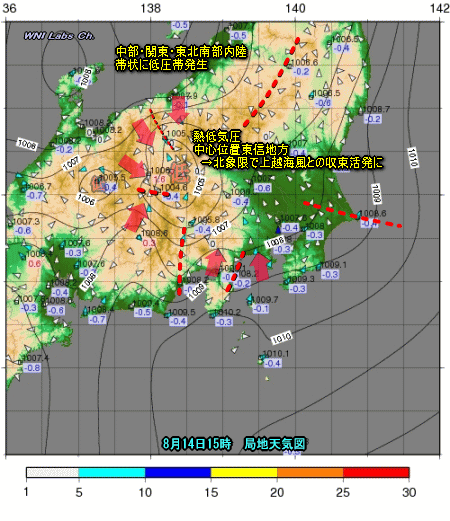
日中の猛烈な気温上昇もあって、長野県付近にガッチリと局地的な熱低気圧(ヒートロー)が発生。
さらに、岐阜県内にもここ数日では見られなかった熱低気圧が発生し、東北方面も含めて内陸部は帯状に低圧部になっています。
したがって、日本海側、太平洋側いずれからも海風が熱低気圧に向かって流れ込みやすい状態。
気温が最も上昇する14時以降、熱低気圧の勢力がピークになって、強まった海風によって暖湿気が内陸に運びこまれたものと思われます。
その際、海風は熱低気圧の位置と山岳などの地形によって複雑な流れ込み方をします。
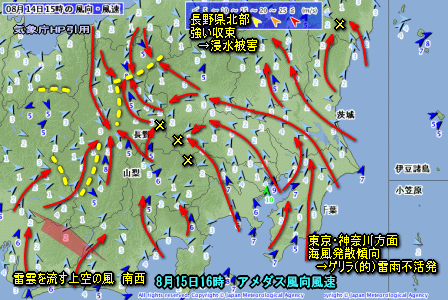
昨日15時の熱低気圧の中心は長野県佐久市の南。
低気圧の東側と北側を反時計回りに流れる風が軽井沢~上田~長野市方面の盆地を流れる風と、上越~野尻湖付近~長野市への風、という二つの風を強めたようです。
このため、二つの風がぶつかる長野市南部で帯状に上昇気流が発生・・・・雷雲が急速に成長したというメカニズムになっていた・・・・・のではないかな?と思います。
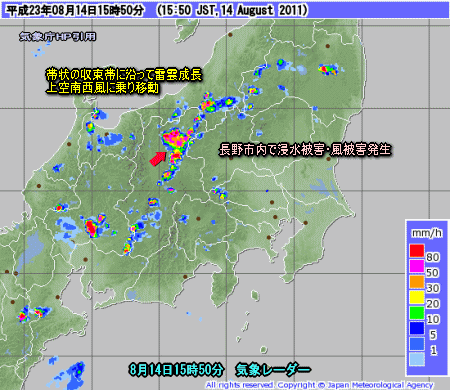
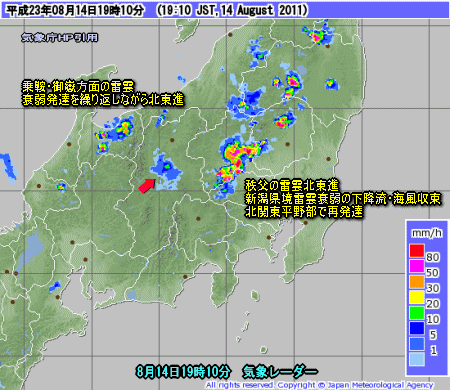
発生した雷雲は上空3000m付近の南西の風に流されて北東方向へ。
松本周辺で発生した雷雲も長野市方面に流れ、長野市南西部では夜になっても衰弱しつつある弱い雷雲による雨がありました。
最後・・・昨日朝の雷雨発生予想は当たっていたのか?ですが・・・・
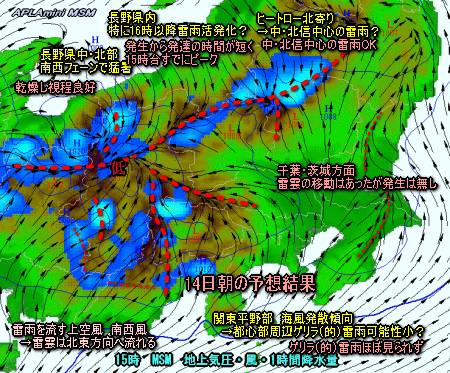
完璧じゃありませんけど、解像度に欠ける計算値を使いながら、そこそこイイ結果になったかも?
今日は予想はどうかしらん?
ご意見・ご質問等は、コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。
可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)
新ブログ URL
大晦日~元日~2日の天気と初日の出(12月31日)
今日は冬型、大晦日は穏やかに(12月30日)
前線通過、今夜から再び冬型へ(12月29日)
冬型緩むも次の寒波が・・(12月28日)
年末年始の空模様・・年末にかけテンポ早く(12月27日)
大晦日~元日~2日の天気と初日の出(12月31日)
今日は冬型、大晦日は穏やかに(12月30日)
前線通過、今夜から再び冬型へ(12月29日)
冬型緩むも次の寒波が・・(12月28日)
年末年始の空模様・・年末にかけテンポ早く(12月27日)
Posted by kasayan at 05:49│Comments(3)
│雑記
この記事へのコメント
kasayanさんおはようございます。
横浜はこのところ連日の熱帯夜です。
海風が強いせいでしょうか、雷雨は横浜沿岸部には届きません。
雷雨によって被害が出るのは避けたいですが、
一時的にでも一息つける涼しさがほしいものです。
ところで、私事ながらほぼ二週間後の試験が気になります。
理科大模試を受けたんですが、解答時間を意識したがために雑になり、ケアレスミスが多かったです。
それ以上に、題意にこたえられない(解けない)問題や、
解答に求められているキーワードが不足していたために減点された部分がありました。
やはり、模範解答にほぼ忠実な解答が求められるのでしょうか。
横浜はこのところ連日の熱帯夜です。
海風が強いせいでしょうか、雷雨は横浜沿岸部には届きません。
雷雨によって被害が出るのは避けたいですが、
一時的にでも一息つける涼しさがほしいものです。
ところで、私事ながらほぼ二週間後の試験が気になります。
理科大模試を受けたんですが、解答時間を意識したがために雑になり、ケアレスミスが多かったです。
それ以上に、題意にこたえられない(解けない)問題や、
解答に求められているキーワードが不足していたために減点された部分がありました。
やはり、模範解答にほぼ忠実な解答が求められるのでしょうか。
Posted by sekky at 2011年08月15日 09:21
>>sekkyさん
横浜に住んでいた頃、こんな暑い日はたいてい東京湾の上でヨットを走らせていました。横浜でも海沿いはイイですよ。
試験直前、色々考えることが多いと思います。
ありきたりのようですが、過去問や模試の模範解答は、短文の中に必要なことから、加点事由程度のことまでぎっしり盛り込まれていると思います。時間をかけて文章を推敲することができるわけですから・・・。
でも、実際の試験で加点事由までは書いている暇などないと思いますし、加点事由を書いていて、本来書くべき基本的なことが薄くなったら本末転倒です。
大胆な言い方をしてしまえば、基本的な情報・・・すなわち、気圧・気温・水蒸気(T-Td・相当温位)と、空気の流れ(水平・垂直)の関係を天気図から読みとれることだけ(恣意的に読みとろうとするとウソ=誤答になります)書いて、風向風速、降水量、水の三態を結論として述べればよいだけと思っていれば良いのではないでしょうか?
短期予報解説資料だって、難しい言葉が出てきても、大枠は基本的なことしか書いてありませんよね。
「こんな当たり前のことだけ書いていて大丈夫なんだろうか?」と心配になる程度でも、しっかり書いている人と薄く書いている人とでは結果が異なってくると思います。採点者は分かっているはずだという思いこみで答案を端折ってしまいがちですが、それをやってしまうと、基本がわかっていないという誤解を生んでしまうと思います。
私は、最初に受けた試験の実技で落ちて、二回目で合格したのですが、二回目の試験の10日前までは何も勉強しませんでした。そして、残り10日でやったことは、基本的なパターンの天気図を何度も眺め、同じ天気図を様々な切り口で解析してまとめる作業だけでした。インターネットで専門天気図を手に入れることができない時代だったので、そうせざるを得なかったのですが、かえってそれが答案を書くという作業の良いトレーニングになったと思っています。
10日あれば、なんでもできます。あせらずに増えすぎた知識をむしろ絞って、簡単なことを丁寧に書くための練習をされてみるのもいかがでしょうか?
大したアドバイスもできずに申し訳ありませんが、気楽に試験を楽しんできてください。
横浜に住んでいた頃、こんな暑い日はたいてい東京湾の上でヨットを走らせていました。横浜でも海沿いはイイですよ。
試験直前、色々考えることが多いと思います。
ありきたりのようですが、過去問や模試の模範解答は、短文の中に必要なことから、加点事由程度のことまでぎっしり盛り込まれていると思います。時間をかけて文章を推敲することができるわけですから・・・。
でも、実際の試験で加点事由までは書いている暇などないと思いますし、加点事由を書いていて、本来書くべき基本的なことが薄くなったら本末転倒です。
大胆な言い方をしてしまえば、基本的な情報・・・すなわち、気圧・気温・水蒸気(T-Td・相当温位)と、空気の流れ(水平・垂直)の関係を天気図から読みとれることだけ(恣意的に読みとろうとするとウソ=誤答になります)書いて、風向風速、降水量、水の三態を結論として述べればよいだけと思っていれば良いのではないでしょうか?
短期予報解説資料だって、難しい言葉が出てきても、大枠は基本的なことしか書いてありませんよね。
「こんな当たり前のことだけ書いていて大丈夫なんだろうか?」と心配になる程度でも、しっかり書いている人と薄く書いている人とでは結果が異なってくると思います。採点者は分かっているはずだという思いこみで答案を端折ってしまいがちですが、それをやってしまうと、基本がわかっていないという誤解を生んでしまうと思います。
私は、最初に受けた試験の実技で落ちて、二回目で合格したのですが、二回目の試験の10日前までは何も勉強しませんでした。そして、残り10日でやったことは、基本的なパターンの天気図を何度も眺め、同じ天気図を様々な切り口で解析してまとめる作業だけでした。インターネットで専門天気図を手に入れることができない時代だったので、そうせざるを得なかったのですが、かえってそれが答案を書くという作業の良いトレーニングになったと思っています。
10日あれば、なんでもできます。あせらずに増えすぎた知識をむしろ絞って、簡単なことを丁寧に書くための練習をされてみるのもいかがでしょうか?
大したアドバイスもできずに申し訳ありませんが、気楽に試験を楽しんできてください。
Posted by kasayan at 2011年08月15日 16:35
at 2011年08月15日 16:35
 at 2011年08月15日 16:35
at 2011年08月15日 16:35Kasayanさん、アドバイスありがとうございました。
迷いが生じて以来、試験勉強の仕方がわからなくなっていたところでした。
落ち着いて基本的な事柄を再確認して行こうと思います!
迷いが生じて以来、試験勉強の仕方がわからなくなっていたところでした。
落ち着いて基本的な事柄を再確認して行こうと思います!
Posted by sekky at 2011年08月16日 06:38



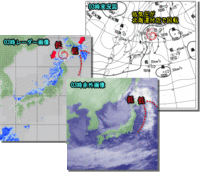




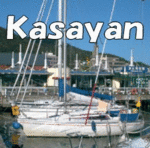


 はてなに追加
はてなに追加 MyYahoo!に追加
MyYahoo!に追加 del.icio.usに追加
del.icio.usに追加 livedoorClipに追加
livedoorClipに追加




